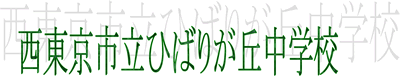10月の給食
更新日:2024年10月31日
毎日の給食
10月31日 ご飯・さばのみそ煮・切干大根のごま酢和え・鶏団子汁・牛乳
さばは、2000年以上前から世界中で食べられていて、美食家で有名なイタリア人も好んで食べていたそうです。「さば紋」と呼ばれる黒い波のような模様が特徴的な魚です。さばなどの青魚に含まれる脂には、脳の成長を活発にしたり、血液をサラサラにする働きがあるDHAやEPAという栄養素が豊富で、さばは青魚の中でも特に豊富です。みそやしょうがはさばの臭みを消してうま味を閉じ込めるので、さばのみそ煮はさばをおいしく食べるのにとても適しています。今日のさばのみそ煮はとても残食が少なかったです。
給食のさばのみそ煮は、煮るというより蒸し焼きのようにしています。しっかりととろみのあるみそだれを作り、魚にかけます。
落し蓋をし、さらに蓋をして1時間ほど蒸し焼きにすると、味がよく入って、少しみその香ばしさも加わり、おいしくできました。
10月30日 ターメリックライス・ギネスシチュー・コルカノン・かぼちゃプリン・飲むヨーグルト
明日、10月31日は「ハロウィン」です。元々は古代ケルト民族のお祭りで、日本のお盆と大晦日と収穫祭を組み合わせたような行事でした。亡くなった人の霊が帰ってくる日だと言われていて、霊に憑りつかれてあの世に連れて行かれないように幽霊のかっこうをしたことが、仮装の始まりだと言われています。今日は、ハロウィン発祥の地であるアイルランドの代表的料理を作りました。ギネスシチューは世界的にも有名な黒ビール「ギネスビール」で煮込んで作るシチューです。コルカノンは炒めたキャベツやベーコンが入ったマッシュポテトです。また、デザートにはハロウィンの飾り「ジャック・オー・ランタン」にちなんでかぼちゃプリンを作りました。今日は飲むヨーグルトもハロウィンバージョンにしたので、「かわいい〜!」と注目してくれている生徒もいました。
今日は本場のギネスシチューと同じように豚肉をギネスビールで煮ました。
ギネスシチューに少しでも似た感じになるように、今日はいつもより材料を大きめに切りました。
ベーコン、玉ねぎ、キャベツを炒め、塩、こしょうで味付けします。
じゃが芋は蒸して潰してマッシュポテトにします。
炒めておいた具材とマッシュポテトをよく混ぜ合わせたら完成です。
かぼちゃプリンのかぼちゃペーストは、牛乳でのばしてとろとろにしてから合わせます。
今日は卵を入れて蒸すのではなく、寒天で固めるプリンです。
カップに注ぎ入れて冷やし固めたら完成です。
10月29日 しそひじきご飯・勝運カツ・豚しゃぶ和え・田舎汁・牛乳
今日は、西東京市と友好都市を結んでいる千葉県勝浦市の料理です。勝浦市は千葉県の南東に位置し、太平洋を臨む温暖な地域です。400年前から続く日本三大朝市のひとつ勝浦朝市や、ビッグひな祭りなどが有名です。太平洋に面した勝浦では漁業が盛んで、カツオの水揚げ量は関東一です。今日の給食で作った勝運(かつん)カツはカツオで作ったサクサクのカツで、勝浦市の学校給食でも食べられています。勝浦市のある千葉県房総半島は「房州ひじき」の名産地でもあるので、手作りのしそひじきふりかけをかけたご飯と組み合わせました。
ひじきはよく味を煮含めて、水分を飛ばします。
ひじきとゆかりを混ぜて作ったふりかけを、ご飯にかけて配食しました。
勝運カツは、しょうゆベースの調味液に漬け込んだカツオに衣を付けて揚げます。
衣がサクサクに揚がりました。にんにくの風味があるので魚が苦手でも食べやすい味です。
10月28日 麻婆なす丼・茎わかめ入り中華スープ・りんご・牛乳
人が一番最初に食べた果物はりんごだと言われていて、8000年も前のことだそうです。りんごにはいろいろな栄養が含まれているので、「一日一個のりんごは医者を遠ざける」や、「りんごが赤くなると医者が青くなる」などのことわざもあります。今日は長野県産の「シナノスイート」という品種です。りんごの品種で有名な「ふじ」と「つがる」を交配してできた品種で、皮はきれいな赤い色をしています。果肉はやや柔らかめで、酸味が少なく甘味が強くてジューシーなりんごです。今日のりんごもとても甘くておいしかったです。
秋なすももうそろそろ終わりの季節です。揚げてから入れると色もきれいに仕上がり、よりおいしくなります。
豆腐や野菜もたくさん入った麻婆なすです。
とても大きなりんごです。良い香りがしていました。
1個ずつ皮をむいて芯を取ります。
10月25日 秋野菜カレーライス・カラフルサラダ・ミルクゼリー柿ソースがけ・牛乳
柿は奈良時代から栽培されていて、アジアやヨーロッパでも「柿」という名前で通じるそうです。柿は渋柿と甘柿に分けられます。実が熟しても果肉が硬いうちは渋みが残る柿を渋柿、熟すにつれて渋が抜けて甘みが強くなるものを甘柿と言います。今日の柿は、市内の農家さんが育てた「太秋」という甘柿です。大きめでさくさくとしていて、果汁が多くて甘い柿です。今日は、柿を粗くすりおろして、レモン汁、砂糖と煮込んで作ったソースをミルクゼリーにかけました。柿のさっぱりとした甘みがおいしく、見た目もきれいなゼリーになりました。
秋野菜カレーには、じゃが芋の代わりにさつま芋が入ります。
れんこんやきのこなど、秋が旬の野菜が他にもたくさん入ります。
さつま芋は蒸してから仕上げに合わせました。甘みがあっておいしいです。
とても大きな柿が届きました。そのまま食べても甘くておいしいのですが、今日はソースにします。
1個ずつ皮をむいて種を取ります。
フードプロセッサーで粗めにすりおろします。
砂糖とレモン汁と合わせて煮込みます。
朝から作って冷やし固めておいたミルクゼリーの上にかけたら完成です。
10月24日 会津ソースカツ丼・野菜の昆布和え・こづゆ・牛乳
今日は、西東京市と姉妹都市を結んでいる福島県南会津郡下郷町の料理、「こづゆ」を作りました。こづゆは山の幸と海の幸を取り合わせた具だくさんの汁物で、会津地方では古くからお祝い事の席でよく食べられてきました。干ししいたけや貝柱でだしをとり、しょうゆベースである点は共通ですが、入れる具材は地域によって少しずつ異なるようです。「会津ソースカツ丼」は、福島県の会津若松市を中心に、昭和初期から親しまれている料理です。ご飯の上にせん切りのキャベツをのせ、甘辛いソースにくぐらせたとんかつをのせて食べます。厚さは薄いですが、大きなカツは満足感がありました。こづゆはほたてや椎茸の出汁がしっかり出ていておいしかったです。
薄いとんかつ用のお肉に衣を付けます。
丸まらないように気を付けながら揚げていきます。
手作りのソースをカツ全体にかけます。
せん切りキャベツはご飯の上にのせました。
こづゆにはホタテの貝柱のフレークを入れました。エキスもたっぷりで良い出汁が出ました。
10月23日 ほうとう・キャベツとじゃこの和え物・黒蜜きな粉ケーキ・牛乳
西東京市では、山梨県北杜市・千葉県勝浦市と友好都市を、福島県南会津郡下郷町と姉妹都市を結んでいるので、給食でその土地の料理を作ることにしました。今日は、山梨県北杜市の料理です。北杜市は山梨県の北部に位置し、北は八ヶ岳連峰、北東はみずがき山など日本を代表する美しい山岳景観に囲まれています。清らかで豊富な水資源、高原性の気候、歴史的な街並みなど、豊かな資源に恵まれた地域です。ほうとうは、小麦粉を練り平らに切った麺をたっぷりの具材とともにみそ仕立ての汁で煮込んだ郷土料理です。そして、31日からIJ学級が宿泊学習で山梨県に行くので、山梨県の有名な郷土菓子の「信玄餅」をイメージした黒蜜きな粉ケーキも作ってみました。今日はたくさんの生徒が「おいしかったです」と声をかけてくれたので嬉しかったです。
今日はほうとう麺なので、うどんに比べて薄くて幅広い麺です。
ほうとうに欠かせないかぼちゃは、煮崩れ内ように蒸しておいて仕上げに入れます。
みそ仕立ての汁です。体が温まります。
ケーキの黒蜜も手作りです。黒砂糖と水を混ぜて、とろみが出るまで煮詰めます。
生地に入れるきな粉は小麦粉と一緒にふるって入れます。
焼き上がったケーキに黒蜜を1個ずつかけたら完成です。
10月22日 焼豚とチンゲン菜のチャーハン・生揚げの中華煮・生きくらげのサラダ・牛乳
生揚げは、豆腐の水分を切ってから高温の油で揚げたものです。油揚げとは違い、中は豆腐の状態を保つようにしっかりとは揚げないので生揚げと呼ばれます。薄く切った豆腐を揚げた油揚げのことを薄揚げと呼ぶことに対し、厚く切った豆腐を揚げた生揚げは厚揚げとも呼ばれます。豆腐の栄養がぎゅっと詰まっているので、たんぱく質やカルシウムが豊富です。味が染み込みやすく、煮物などの料理に適しているので、今日は中華煮にしました。今日はどの料理も人気でした。
今日のサラダのきくらげは、白い生きくらげです。
中華煮は生揚げだけでなく野菜やお肉もたくさん入って栄養満点です。
10月21日 梅じゃこご飯・ぶりの照り焼き・花野菜の和え物・芋の子汁・牛乳
東北地方では、秋になると旬の里芋が入った汁物を大きな鍋で作り、大勢で食べる「芋煮会」が行われます。ここでふるまわれる汁は「芋の子汁」「芋煮」と呼ばれる郷土料理です。秋田県や岩手県では鶏肉、宮城県や福島県では豚肉、山形県では牛肉を入れるなど、地域によって具材や味付けにも特徴があります。今回は、にんじん、大根、ごぼう、きのこ、こんにゃく、豆腐、鶏肉などを入れて、味付けにしょうゆとみそを使った岩手県風の芋の子汁を作りました。急に涼しくなった今日のような日にはぴったりの汁物でした。
10月17日 ドライカレーパン・レンコンチップス・ミックスサラダ・ファソラーダ・シャインマスカット・牛乳
明日はいよいよ合唱祭ということで、今日は応援メニューにしました。極端に辛いものは、のどに刺激を与えてしまうので、今日のカレーパンは辛さ控えめです。レンコンは、のどの渇きや痛み、炎症の改善に良いとされています。ちなみにファソラーダはギリシャの伝統的な白いんげん豆のスープです。今日は料理名の頭文字をつなげると実は「ド・レ・ミ・ファソラ・シ」となっています。生徒は気付いてくれるかな…とドキドキしていましたが、ちゃんと気付いてくれていました。どの料理も好評だったようで、おかわりじゃんけんも白熱し、残食はとても少なかったです。明日の合唱祭では、どのクラスも練習の成果を発揮できるように応援しています!
カレーパンはドライカレーから手作りです。
今日は焼きカレーパンです。コッペパンの間にドライカレーをたっぷり入れて、チーズをかけて焼きます。
チーズがとろけて焼き色もほんのりついておいしそうに出来上がりました。
れんこんはとても薄くスライスします。
少量ずつ油でパリパリに揚げます。
きれいに揚がりました。
ミックスサラダの上に乗せて配缶し、一緒に食べてもらうようにしました。
ファソラーダには、柔らかく煮た白いんげん豆が入ります。チリパウダーやローリエ、オレガノなどのスパイスも入っていつものスープとは香りや味の雰囲気が少し違います。
デザートはシャインマスカットです。甘くてちょうど食べ頃のものが届きました。
保健給食委員の生徒が、献立を書くホワイトボードにドレミをわかりやすく書いてくれていました。
10月16日 ホイコーロー丼・華風大根・春雨スープ・牛乳
ホイコーローは、漢字で「回鍋肉(回る鍋の肉)」と書きます。お肉を鍋の中でくるくる回しながら炒めるからこの字を書くのではなく、一度調理した肉をもう一度鍋に戻した調理するという意味からこの字を書きます。豚肉と野菜を炒めて合わせ、トウバンジャンやテンメンジャンなどで味を付けた、中国の四川料理の一つです。四川ではニンニクの芽を使ってとても辛い味付けにするそうですが、日本ではキャベツを使い、みそやオイスターソースで味付けしたものが一般的です。今日はキャベツをたっぷり62kgも使って作りました。
キャベツは蒸してから合わせましたが、釜からあふれてしまいそうでした。
10月15日 吹き寄せおこわ・ししゃものフライ・根菜のみそ汁・お月見団子・牛乳
今日は「十三夜」です。9月17日が十五夜でしたが、十三夜は十五夜の約1か月後にめぐってくる月のことを言います。一番きれいな月が見えるという十五夜の次に美しい月が見えるとされ、十五夜と十三夜の2度お月見をすると縁起が良いと言われています。十三夜は栗が多く収穫できる時期なので「栗名月」とも呼ばれます。今日は十三夜に合わせて、栗を入れた秋らしい吹き寄せおこわと、みたらしのたれをかけたお月見団子を作りました。夜になるときれいな月が見えていました。
給食では今年初の栗です。炊飯器でお米と一緒に炊き込みました。
炒め煮にした他の具材を炊きあがったおこわに混ぜ込みます。
紅葉の形に抜いたにんじんを上から散らします。
秋らしいきれいなおこわができました。
お月見団子は一人3個。約1800個きれいに丸めました。
ゆでたお団子に手作りのみたらしたれをかけたら完成です。
10月11日 ごま塩ご飯・すき焼き煮・じゃが芋とれんこんの青のり炒め・牛乳
すき焼きは、肉に砂糖としょう油の味がバランスよく調和した日本独特の肉料理です。関西地方で江戸時代に「鋤」という農作業道具の金属部分を鉄板代わりにして魚や貝などを焼く「魚すき」や「沖すき」と呼ばれる料理が食べられていたことが、すき焼きの語源だと言われています。その他に、薄く切った肉を意味する「すき身」から付けられたという説もあります。牛肉を使うようになったのは明治時代に入ってからで、東京ではその頃は「牛鍋」という名前でしたが、その後、関西と関東で呼び名が統一され、「すき焼き」となったそうです。
10月10日 キャロットライスほうれん草クリームソースがけ・レバーのマリアナソース・かぼちゃのさっぱりサラダ・ジョア(ブルーベリー)
10月10日は、数字の10を横にして2つ並べると、目とまゆ毛の形に見えることから、目の愛護デーになっています。目の健康に関わる代表的な栄養素である「ビタミンA」は、目を守る粘膜を強くし、目の乾燥を防ぐ働きがあり、レバーやうなぎ、卵黄などに多く含まれています。にんじんやほうれん草、かぼちゃなどの緑黄色野菜に多く含まれる「β-カロテン」は、体内で効率よくビタミンAに変換され、目の健康維持に役立ちます。また、ほうれん草やブロッコリーに多く含まれる「ルテイン」という成分は、光による刺激から目を保護する網膜色素を増加させると考えられています。今日の給食は、これらの栄養素が豊富な食材が多く取り入れられています。レバーは苦手意識のある生徒も多く、配膳の時にはあまり嬉しそうではなかったですが、食べてみると思ったよりもおいしかったという生徒が多くいました。
今日のご飯は細かく刻んだにんじんを入れたキャロットライスです。
ほうれん草はこんなにたくさん使います。
クリームソースを作って最後にほうれん草を入れます。彩りもきれいです。
レバーはしょうが、しょうゆ、酒で下味をつけて、片栗粉をまぶして揚げます。
ケチャップ、ソース、砂糖、赤ワインで作ったマリアナソースを絡めると、とても食べやすくなります。
サラダのかぼちゃは角切りにして、蒸してから他の野菜と合わせました。今日は酸味のきいたドレッシングでさっぱりと仕上げます。
10月9日 ばら天丼・ひじきの炒め煮・かきたま汁・牛乳
天丼は、江戸時代の後期に手早く食事を済ませるために考案され、屋台で出されたそうです。江戸の名物料理として親しまれ、関東大震災後には家や仕事を失って里帰りした人が故郷で天丼を再現したことで、全国へ普及していきました。今日のばら天丼は、ひと口サイズのえびとまいたけの天ぷらをたくさん作り、ごはんとたれと天ぷらを二段重ねにして盛り付けました。とても好評で、大盛りでおかわりしている生徒もたくさんいました。
小房に分けたまいたけとえびにそれぞれ衣を付けてぱらぱらと油の中に入れます。
小さいので数分でカラッと揚がります。
バットにご飯を入れ、手作りのたれをかけます。
まいたけの天ぷらを散りばめます。
えびの天ぷらも同じように散りばめます。
天ぷらの上からたれをかけます。この上にまたご飯、たれ、天ぷら、たれと同じように重ね、2段重ねにします。
10月8日 キムチラーメン・棒ぎょうざ・梨・牛乳
梨のシャリシャリとした食感は石細胞と呼ばれるもので、体内に入ると食物繊維と同じ働きをしてお腹の中をきれいにしてくれます。今日の梨は、「にっこり」という栃木県で開発されたオリジナルの品種です。にっこりという名前は、栃木県の有名な観光地である「日光」と、「梨」の読みである「り」から名付けられたそうです。とても大きい品種で、1個で800グラムを超えるほどの大きさです。酸味は少なく、甘くてみずみずしいのが特徴です。今日の梨も甘くておいしかったです。
梨は一つ一つ手で皮をむいて芯を取っています。
10月7日 さつま芋ご飯・千草焼き・梅おかか和え・生なめこのみそ汁・牛乳
なめこは秋にブナの枯れ木や切り株などに生えるきのこで、全体が独特のぬめりでおおわれているのが特徴です。このぬめりには、腸内の善玉菌の増殖を促進して腸内環境を改善したり、胃や気管支の粘膜を守って感染症にかかりにくくする手助けをしたりする働きがあります。なめこは水煮のパック詰めになって一年中食べられますが、しめじのような株の状態の生なめこはこの時期にしか食べられません。今日はご飯もさつま芋ご飯なので、一気に秋らしい献立になっていました。
今日のさつま芋はシルクスイートでした。きれいに洗って皮のまま使います。
昆布と一緒にご飯に炊き込みました。釜を開けると良い香りがしました。
生なめこはしめじのように株になっています。水煮のものと比べるととても大きいです。
なめこの成分で汁がとろとろです。
10月4日 ご飯・小松菜ふりかけ・里芋の揚げ煮・吉野汁・牛乳
里芋は、名前のとおり里で採れるので里芋と呼ばれています。稲よりも早く縄文時代に渡来しており、当時はさつま芋やじゃが芋がまだなかったため主流のエネルギー源となっていたようです。里芋には独特のぬめりがありますが、その成分には消化促進や動脈硬化の予防、免疫力を高める働きなどがあります。貯蔵性が良いので一年中出回っていますが、旬は秋から冬にかけてです。汁物や煮物の里芋は苦手でもこれは好きという生徒も多いようで、全クラス合わせても残食はほとんどありませんでした。
里芋は小さめの乱切りにします。
片栗粉をまぶして油でカラッと揚げます。
揚げると外はサクッとしますが、里芋なので中はとろっとします。
甘辛いみそだれをしっかり絡めたら完成です。
10月3日 手作りココア米粉パン・マカロニサラダ・クリームシチュー・牛乳
今日のパンは、給食室で手作りしたものです。いつもの給食のパンは小麦粉で作られていますが、今日は米粉を使っています。米粉はうるち米を粉砕して細かい粉状にしたもので、お団子などの和菓子を作る時に使う上新粉なども米粉の仲間です。米粉には小麦粉よりも良質なたんぱく質が含まれ、腹持ちが良く、もちもちとした食感が楽しめます。米粉を使うことにより、日本の水田の有効活用や、稲作文化の継承、食料自給率の向上につながるため、米粉の消費拡大については国の政策も進められています。いつものパンと比べると小ぶりに見えますが、ぎゅっと詰まっているので食べてみると意外とお腹がいっぱいになります。「もちもちしていておいしかった」という声がたくさん聞かれました。
米粉ミックス粉、ドライイースト、ココア、砂糖をよく混ぜ、ぬるま湯をを加えてよく捏ねます。
100個分ずつ分けて生地を作りましたが、捏ねるのは大変です。
表面がきれいになるように、1個1個丁寧に丸めます。
40℃で30分発酵させてから、170℃で20分焼いたら完成です。
10月2日 わかめご飯・なすとれんこんのはさみ揚げ・みそけんちん汁・牛乳
なすの旬は6月から10月頃までの夏から秋にかけてです。その中でも9月の終わりから10月頃に採れるなすのことを「秋なす」と言います。この時期は、昼と夜の気温差が大きいため、実が引き締まり、旨味のつまったなすができます。れんこんは、これから冬にかけて旬を迎えます。煮物や炒め物、サラダなどいろいろな食べ方でおいしく食べることができます。なすとれんこんはどちらも油で揚げるとおいしく、苦手な人でも食べやすくなるので、今日はお肉をはさんで揚げたはさみ揚げにしました。なすはジューシーで、れんこんはシャキシャキとした食感が残っておいしかったです。生徒からも「おいしい」の声をたくさんいただき、残食もとても少なかったので良かったです。
なすは切り落とすのではなく切り込みを入れます。
れんこんはなるべく同じ厚さになるように一枚一枚切ります。
2枚のれんこんではさむので、約1200枚切りました。
なすは切り込みを入れたところにお肉をはさみ、衣をつけます。
れんこんは2枚でお肉をはさみ、衣をつけます。
油でからっと揚げたら完成です。
10月1日 鶏ごぼうピラフ・アクアパッツァ・じゃが芋とベーコンのスープ煮・ぶどう(甲斐キング)・牛乳
アクアパッツァはイタリア南部のナポリ地方の郷土料理です。白身魚をオリーブオイルで炒め、水やトマト、白ワインなどで煮込んで作ります。ナポリの漁師たちが売れ残った魚でスープを作ったのがこの料理の始まりだそうです。イタリア語で「アクア」は「水」、「パッツァ」は「暴れる」や「狂った」という意味であり、もともと船の上で作られていたため、鍋が大きく揺れることや熱した油に水をそそぐ様子から名付けられたと考えられています。今日は、マトウダイという白身魚を使い、彩りのきれいな野菜も入れたアクアパッツァを作りました。
魚は軽く下味をしてからカップに入れ、上に野菜をのせます。
オリーブ油やにんにく、玉ねぎなどで作ったソースとトマトを混ぜて上からかけます。
蒸し焼きにしたら完成です。彩りもきれいです。