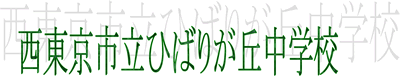8.9月の給食
更新日:2024年9月30日
毎日の給食
9月30日 かて飯・さつま芋コロッケ・つみっこ・牛乳
今日は、1年生が明日、校外学習で行く「川越」のある「埼玉県」にちなんだ料理です。川越と言えば「さつま芋」が有名ですが、それは昔、江戸で焼き芋が大流行したのがきっかけでした。川越で栽培した芋は質が良く、また、川越からは江戸に運びやすかったこともあり、さつま芋の大産地になったそうです。今日は、さつま芋を蒸してつぶし、コロッケにしました。「かて飯」は、米の生産量が少ない地域でご飯の量を増やすために具材を加えたことからできた料理とされています。「つみっこ」は、昔から小麦の栽培が盛んでうどん文化が根付いている本庄市や秩父地方の料理です。小麦粉を水で練って作った生地を「つみとる」ようにちぎって鍋に入れたことからつみっこと呼ばれるようになったと伝わっています。
かて飯の具材は炒め煮にします。たくさんの具材が入ります。
少し味付けして炊いたご飯とよく混ぜ合わせると、炊き込みご飯のような仕上がりになります。
今日のコロッケはさつま芋です。蒸してつぶします。
炒めたひき肉や玉ねぎなどを加えてよく混ぜます。
小判型にして、衣を付けて揚げます。
カリッとしておいしそうな色に揚がりました。
つみっこの生地は、シンプルに小麦粉を水で練って作ります。
「つみとる」ように一口大にちぎります。
そのまま汁に入れるとにごりやすいので、下ゆでしてから入れました。
昆布とさば節の出汁に加え、野菜やお肉からも出汁が出ておいしくできました。
9月27日 ご飯・鶏肉のねぎ塩焼き・わかめとじゃこの和え物・呉汁・牛乳
呉汁は、日本各地に伝わる郷土料理のひとつです。呉汁の「呉」とは、大豆を水に浸け、やわらかくしてすりつぶしたもので、その「呉」をみそ汁に入れたものを呉汁と言います。秋に収穫された大豆が出回るこれからの季節においしい料理です。大豆と色々な野菜の入った呉汁は、栄養価の高く、体も温まります。給食では、水に浸してからゆでた大豆を、ミキサーで細かくつぶして入れました。目にはほとんど見えない細かさでしたが、大豆の風味と甘みは感じられておいしかったです。
大豆を柔らかくゆでてからミキサーにかけます。
汁物に入っている豆をあまり好まない生徒も多いので、かなり細かくしました。
野菜もたくさん入って栄養満点です。
9月26日 チキンカレーライス・小松菜サラダ・みかんゼリー・牛乳
ゼリーはジュースなどの液体を凝固剤で固めて作られています。凝固剤には寒天、ゼラチン、アガーなど種類があり、それぞれ性質に特徴があります。寒天は海藻類からできていて、凝固力が強く、常温でも溶けません。歯切れがよく、ほろっと崩れる食感が特徴です。ゼラチンは牛や豚のコラーゲンが原料で、体温で溶けるので口溶けが良いです。アガーは海藻やマメ科の種子などから抽出したもので、30〜40℃で固まり、常温でも型崩れしにくく、寒天とゼラチンの間のようなぷるんとした食感が出ます。今回はアガーを使って作りました。少しやわらかい仕上がりでしたが、のど越しが良くおいしかったです。
みかんゼリーは、最初にみかんの缶詰をカップに入れておきます。
ゼリー液を作り、みかんの上から注ぎ入れ、冷やし固めます。
今日は試食会が行われました。
保護者の皆様にも、生徒と同じように配膳していただきました。
皆さん「おいしい」と言って食べてくださいました。
栄養士からは、中学生の食事についてや給食作りの様子、給食での取組等についてお話しさせていただきました。
9月25日 サイファン・白身魚のから揚げ・生きくらげと卵のスープ・牛乳
今日のスープに入っている生きくらげは、西東京市内の農家さんから届いたものです。しいたけ、きくらげ、ひらたけなどの「きのこ」専門の農家さんで、朝の2時に起きて収穫したものを届けてくださるので、とても新鮮です。普段給食では乾燥きくらげを使っていますが、生のきくらげは食感や風味が違います。卵スープに入れたらとてもおいしかったです。
大きくて肉厚な生きくらげです。
卵の黄色、にんじんのオレンジ色、チンゲン菜の緑色にきくらげの色が入って、色鮮やかなスープになりました。
9月24日 けんちんうどん・磯香和え・二色きな粉おはぎ・牛乳
お彼岸には、お墓参りをして、ご先祖様に日頃の感謝を伝えます。春と秋で年に2回ありますが、秋のお彼岸は9月22日の「秋分の日」をはさんで前後3日間を合わせた1週間のことを言います。秋のお彼岸には、昔からおはぎをお供えする習慣があります。おはぎは、もち米を混ぜて炊いたご飯を、米粒が残る程度につぶして丸め、あんこやきな粉で包んだ食べ物です。「おはぎ」という名前は、秋のお彼岸の頃に咲く「萩」の花が由来と言われています。給食では、普通のきな粉とうぐいすきな粉の、2種類のきな粉をまぶしたおはぎを作りました。色の違いがしっかり出てきれいに仕上がりました。
もち米を混ぜて炊いたご飯を、粒が残る程度につぶします。
一つ一つ丸めてきな粉をたっぷりまぶします。
カップに2種類のおはぎを1個ずつ入れます。色の違いがはっきりわかってとてもきれいです。
9月18日 マーガリンパン・ムサカ・ホルタ・レヴィシアスーパ・ジョア(ストロベリー)
今日はギリシャの料理です。「ムサカ」は、なす、じゃが芋、ミートソース、ホワイトソースを重ねてオーブンで焼いた、ギリシャの代表的な料理です。「ホルタ」はギリシャ語で野草を意味する言葉ですが、料理名でホルタと言うとゆでた青菜のサラダになります。ギリシャではレモン汁やオリーブオイルをかけて食べるので、給食ではレモン汁とオリーブオイルを使って作ったドレッシングでほうれん草を和えたサラダにしました。「レヴィシアスーパ」のレヴィシアは「ひよこ豆」、スーパは「スープ」のことで、ひよこ豆が入ったスープです。ムサカは苦手な生徒も多いなすが入っていましたが、残食は少なかったです。
なすはミートソースの中に入れて煮込みました。お肉だけでなく実は大豆も入れています。
今日のホワイトソースは豆乳で作りました。なめらかに仕上がるように丁寧に作っています。
蒸したじゃが芋をカップに敷き詰めます。
じゃが芋の上になす入りのミートソース、ホワイトソースの順に入れます。
最後に上からチーズをのせてオーブンで焼いたらムサカの完成です。
ホルタには大きなザル2個分のほうれん草を使いました。
レヴィシアスーパのひよこ豆は柔らかくホクホクとした食感になるまでゆでてから入れます。
野菜がたくさん入って、優しい味のスープになりました。
9月17日 里芋ご飯・にぎすのから揚げ・即席漬け・お月見汁・牛乳
今日、9月17日は十五夜です。十五夜には、すすきやお団子をお供えして月を眺めます。十五夜に見る月は「中秋の名月」と言われ、一年で一番きれいな月とも言われています。また、この時期には里芋がたくさん採れることから、「芋名月」とも呼ばれます。今日の給食では、蒸した里芋を混ぜた「里芋ご飯」と、お月見団子に見立ててかぼちゃを練り込んで黄色くしたお団子とうさぎ型のかまぼこを入れた「お月見汁」を作りました。今日の夜は、きれいな月が見られると良いですね。
里芋は蒸しておいて、調理した他の具材にさっくりと合わせました。
白玉粉にかぼちゃを混ぜて黄色くします。
一つずつ丁寧に丸めます。一人3個くらいはあるので1800個は丸めています。
ゆでるとよりきれいな黄色になりました。
月で餅をついているうさぎの可愛らしい蒲鉾も入れました。
お月見団子たっぷりの具だくさんな汁になりました。
9月13日 ご飯・のりのつくだ煮・ピリ辛肉じゃが・小松菜の炒め物・牛乳
肉じゃがは日本人が考えた料理ですが、もとの料理はビーフシチューだったと言われています。昔、イギリスに留学していた海軍の軍人がイギリスで初めて食べたビーフシチューがとてもおいしかったので日本でも食べたいと思い、船での食事に作るように部下に命じました。船の調理員はビーフシチューを知らなかったので、色や形、味などを聞きながら、当時貴重だった赤ワインの代わりにしょうゆをいれるなど試行錯誤を重ねた結果、現在の肉じゃがのような料理が出来上がったそうです。ビーフシチューとは全然違う料理でしたが、日本で親しまれる味になりました。今日の肉じゃがは少しトウバンジャンを入れてピリ辛にしましたが好評だったようです。
じゃが芋が煮崩れないように、優しく混ぜます。
つくだ煮ののりは小さくちぎって水でよくふやかします。
調味料を入れてよく煮詰めます。手作りなのでのりの食感も少し残っていておいしいです。
9月12日 チンジャオロース丼・おこげのスープ・梨・牛乳
今日の梨は、西東京市内の果樹園で採れたものです。西東京市では梨がたくさん栽培されていて、「保谷梨」という名前で特産品の一つにもなっています。梨は一度収穫してから食べ頃になるまで置いておくことが多いのですが、保谷梨は木になったまま完熟させるの「木成り熟成」で栽培されます。この方法で梨を栽培することで、ほどよく甘く、ジューシーな果肉、爽やかな食感を楽しめるようになります。また、5月頃から良質な実だけを残す「摘果」を繰り返し、玉が大きなものを厳選して育てているのも特徴の一つです。今日は「あきづき」という品種で、酸味はほとんどなく、甘みが強くておいしかったです。
採れたての保谷梨です。しっかり食べ頃になっています。
一つ一つ皮をむいて芯を取っています。
9月11日 ご飯・鮭のホイル焼き・白菜の甘酢漬け・けんちん汁・牛乳
魚の調理方法は焼く、煮る、揚げるなどさまざまありますが、ホイル焼きは蒸し焼きという調理方法です。蒸し焼きは、食材に直接火を当てずに包み込んで焼くので、ふっくらと柔らかく仕上げることができます。また、ホイル焼きにすると食品のもつ旨味や栄養素が流れ出ることがなく、香りも包み込まれるのでよりおいしく食べることができます。今日の鮭は銀鮭で、脂がのっていて身がふっくらとしていておいしいです。残ったたれをご飯にかけて食べてくれている生徒もいました。
さっと炒めて水気を切った野菜とみそマヨソースを合わせておきます。水っぽくなるので8個分ずつ作りました。
アルミホイルに鮭を並べ、みそマヨソースを絡めた野菜を上からのせます。
一つ一つ丁寧に包みます。
仕上がりはこのようになりました。アルミホイルで包まれているので香りも閉じ込められていて、開けた時にとても良い香りがしました。
9月10日 スパゲティナポリタン・キャベツのサラダ・ブルーベリーマフィン・牛乳
スパゲティと言えばイタリアを思い浮かべる人も多いと思いますが、ナポリタンは日本で生まれた料理です。玉ねぎやピーマン、肉などと一緒にスパゲティをトマトケチャップで炒めた料理で、横浜にあるホテルのシェフが考えました。ゆでたスパゲティに塩、こしょう、トマトケチャップを和えたものを米兵が食べているのを知り、アレンジを加えて生み出したそうです。また、一見日本発祥という感じのしない、ドリアとプリンアラモードも、この横浜のホテルで誕生し、日本全国へ広がっていったそうです。スパゲティはいつも人気がありますが、今日のナポリタンも大人気でした。
具材を炒め、ケチャップなどで味付けします。酸味はほどよく飛ばしています。
少し硬めにゆでためんとよく混ぜ合わせます。
マフィンのブルーベリーは市内の農家さんに届けてもらいました。冷凍ですがフレッシュな感じがしておいしいです。
9月9日 親子丼・とうがんの菊花あんかけ・なすのみそ汁・牛乳
9月9日は「重陽の節句」です。重陽の節句は「菊の節句」とも呼ばれ、菊の花を浮かべたお酒を飲んで、無病息災を願う習慣があります。菊は昔から薬草として使われ、寿命を延ばす力があるとされて親しまれてきました。また、重陽の節句には、不老長寿を願って秋なすを食べる風習もあります。今日は、重陽の節句に合わせ、食べられる黄色い菊の花びらを入れたとうがんのあんかけと、なすのみそ汁の献立にしました。生徒にとっては苦手な食材や食べ慣れない食材が多かったかもしれませんが、伝統的な行事に合わせた食事を理解してもらえていたら嬉しいです。
食べられる菊の花びらです。一枚一枚花びらをはがしました。
冬瓜をやわらかく煮てとろみをつけ、小ねぎと菊の花びらで色鮮やかに仕上げました。
みそ汁のなすは素揚げをしています。
なすにひと手間加えるだけで、見た目がきれいに仕上がり、味もよりおいしくなります。
9月6日 ご飯・ハンバーグ・ブロッコリーとコーンのサラダ・リボンパスタのスープ・牛乳
ハンバーグは、もともとはタルタルステーキという料理だったと言われています。タルタルステーキは、生のお肉を細かくしたものに生卵をのせて混ぜて食べる料理で、タタール人が食べていました。そのタルタルステーキを焼いたものがドイツのハンブルグという町で作られたことで、ハンブルグという名前からハンバーグと呼ばれるようになったそうです。ハンバーグはやはり大人気でした!おかわりのごはんにハンバーグのソースをかけて食べてくれている生徒もいました。
人数分に分けたたねを一つ一つ空気抜きし、小判型に形を整えます。
ソースも手作りです。焼いたハンバーグから出た肉汁も加えました。
9月5日 鶏とめかぶのご飯・さばの文化干し・かりぽり和え・沢煮碗・牛乳
めかぶはわかめの一部です。わかめの根本の部分にある、葉や茎がかたくなっている部分がめかぶで、上のひらひらとした葉の部分がわかめです。めかぶなどの海藻は、低エネルギーでヨウ素や食物繊維が豊富です。ヨウ素は新陳代謝を活発にしたり、甲状腺ホルモンをつくったりするため、成長期に大切な栄養素です。めかぶからとろみが少し出るので、味がよく絡んでおいしくできました。
めかぶは水で戻すととろみが出てきます。
めかぶは食感が残るように具の最後に合わせました。
9月4日 オレンジフレンチトースト・オリエンタルサラダ・マカロニのクリーム煮・ぶどう(ピオーネ)・牛乳
フレンチトーストは、卵に牛乳を混ぜて砂糖を加え、そこにパンを浸し、バターでこんがりと焼いた料理です。卵と牛乳に浸すことで、パンがしっとりと柔らかくなるので、時間が経って硬くなってしまったパンをおいしく食べるのにおすすめの料理法です。フランスでは、普通のパンと比べると硬めなバゲットと呼ばれる棒状のフランスパンで作ることが多いです。今日は、牛乳をオレンジジュースにアレンジして作りました。
オレンジジュース入りの卵液にパンをしっかり浸します。
きれいな色に焼き上がりました。
9月3日 もろこしご飯・いかのかりんと揚げ・レタスと小松菜のおひたし・具だくさんみそ汁・牛乳
レタスは涼しくて乾燥した気候を好む野菜で、気温20度前後で最もよく育ちます。そのため、季節ごとに産地を変えて、一年中日本のどこかで栽培されています。レタスの95%は水分でできていて、その他にビタミンC、カルシウム、食物せんいなどをバランスよく含みます。サラダのイメージが強い野菜ですが、炒め物や鍋、スープなど加熱する料理にもおすすめです。今日はおひたしにしました。
とうもろこしは皮をむいて実をそぎ落としてお米と一緒に炊飯器に入れて炊きます。
芯からもうま味が出るので一緒に入れて炊飯しました。
おひたしに入れるたくさんのレタスは一口大に切ります。
シャキシャキ感が残るようにさっとゆでます。生だとすごい量ですが、火を通すとカサが減ってたくさん食べられます。
9月2日 ツナピラフ・ビーンズサラダ・トマトポトフ・牛乳
昨日、9月1日は「防災の日」でした。今から101年前の1923年9月1日に発生した関東大震災を忘れないため、また、毎年台風が多く来るこの時期に防災への備えを確認してもらうために、9月1日が防災の日になりました。今日の給食は、災害時への備蓄に良い食品を組み合わせて作られています。コーンやツナ、トマト、ミックスビーンズなどの缶詰、カットわかめや大豆などの乾物、じゃがいもやにんじん、玉ねぎなどの野菜は長期間保存することができます。お米は無洗米やレトルト、アルファ化米を用意しておくのがおすすめです。飲み物も、冷蔵庫に入れずに1年以上保存できるものもあります。この機会に災害への備えができているか確認してみると良いですね。
今日はピーマンとパプリカも入れて彩り良く仕上げます。
給食のように、具を作ってレトルトのご飯に混ぜてもピラフが作れます。
ミックスビーンズは水煮になっているのでそのまますぐに使えます。
ポトフはトマト缶とケチャップを入れるだけでいつもと違った味わいを楽しめます。
8月30日 冷やし中華・ジャンボシュウマイ・のり塩ポテト・牛乳
冷やし中華の誕生には色々な説がありますが、中華料理店の店主が、ざるそばやそうめんの好きな日本人向けに考えたのが始まりだと言われています。このお店の冷やし中華は、蒸しためんに油をからませてお皿に盛り、その上にたけのことしいたけを煮たもの、糸寒天、チャーシュー、きゅうりを細長く切ったものを彩りよくならべて乗せ、薄く焼いて切った卵を真ん中にのせて、富士山をかたどっているそうです。冷やし中華のたれは、しょうゆ、ごま、みそなど色々ありますが、今日は食べやすいように酸味を控えめにし、すりごまやごま油も入れてまろやかなしょうゆ味のたれに仕上げました。おかわりしている生徒もたくさんいて、ジャンボシュウマイとのり塩ポテトも含めて今日は残食が少なかったです。
冷やし中華のたれ用に、鶏ガラで出汁を取ります。
すりごまとごま油を入れてまろやかなたれにしました。この後しっかりと冷やします。
麺はゆでてしっかり水で冷やします。
野菜とハムは麺の上に乗せました。
麺・野菜→炒り卵→たれの順で盛り付けます。
8月29日 しょうがご飯・生揚げのスタミナあんかけ・糸寒天の和え物・とうがんのみそ汁・牛乳
しょうがは一年中食べることができ、薬味として使われることの多い野菜です。今日のご飯に入っているしょうがは、夏から秋にかけて出回る「新しょうが」です。新しょうがとは収穫したてのしょうがのことで、辛みが少なくみずみずしさがあるため、「ガリ」などの漬物として食べられることも多いです。新しょうがの爽やかな香りがおいしいご飯でした。スタミナあんとの相性も良いようで、あんをご飯にかけて食べている人もいました。
しょうがの辛味が苦手な人もいるので、今日のしょうがはすごく細く切りました。
こんなに細い仕上がりになりました。
ご飯に混ぜる具材を炒め煮にし、最後にしょうがをさっと合わせます。
酒としょうゆを入れて炊いたご飯に具材を混ぜ合わせます。しょうがの香りがふわっとしてきます。
8月28日 夏野菜カレーライス・コールスローサラダ・サイダーポンチ・牛乳
今日から2学期の給食が始まりました。2学期最初の給食は、夏野菜がたくさん入ったカレーライス、コールスローサラダ、サイダーポンチで、全体的にさっぱりとして暑い日でも食べやすいメニューです。保健給食委員の生徒を中心に協力して準備や片付けをしたり、おかわりじゃんけんをしたりと、いつもの給食時間の風景が戻ってきました。元気にたくさん食べている生徒の姿を久しぶりに見られて嬉しいです。2学期もよろしくお願いします。
今日のカレーにはトマトがたくさん入ります。湯むきして角切りにしました。
なす、ピーマン、パプリカは素揚げして仕上げに合わせます。
赤、黄色、緑、紫の野菜が入って彩りがきれいです。