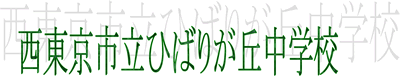12月の給食
更新日:2024年12月24日
毎日の給食
12月24日 トマトファルファッレ・ローストチキン・リース風ドーナツ・ぶどうジュース
2学期最後の給食は、クリスマスイブなのでクリスマスメニューにしました。ファルファッレとはパスタの一種で、リボンのような形をしたパスタです。プレゼントにかけられているリボンをイメージし、クリスマスカラーの野菜も飾りました。クリスマス料理の定番でもあるローストチキンは、にんにく、白ワイン、しょうゆ、はちみつなどで鶏肉を漬け込んで、オーブンで焼いています。ドーナツは、クリスマスリースをイメージして、東京の八丈島で採れた明日葉の粉を生地に混ぜ込んできれいな緑色にし、雪のように粉砂糖をふりかけました。どの料理も大好評で、生徒たちはとても喜んでいました。完食のクラスも多くて、給食室も嬉しい2学期最終日でした。冬休み中も規則正しい生活を心がけて、風邪やインフルエンザなどに負けず、元気に過ごしてほしいです。2学期もありがとうございました。
にんじんとパプリカは、星形にして後で飾ります。
トマトソースにブロッコリーを入れるとクリスマスカラーできれいです。
バットに盛り付けてからにんじんとパプリカをきれいに飾ります。
華やかに仕上がりました。リボン型のパスタがかわいいです。
ローストチキンは、鶏肉を調味液によく漬け込んでから焼きます。
ジューシーに焼き上がりました。焼き色もついておいしそうです。
ドーナツは明日葉の緑色がきれいです。ドーナツ型がないので一つずつ手で形を作ります。
油で揚げると少しきつね色になりますが、中は緑色のまま仕上がっています。
カップに入れ、粗熱が取れたら粉砂糖を雪のようにふりかけます。
今日はどのクラスもいつも以上にきれいに片付けてくれていました。嬉しいです。
12月23日 キンパ風混ぜご飯・大学芋・西東京野菜タップリキムチなべ・牛乳
今日は、めぐみちゃんメニューの第3弾で、2年A組グループが考案した「西東京野菜タップリキムチなべ」です。冬が旬の白菜で作られているキムチと、西東京市の冬野菜をふんだんに使った健康的な鍋を考えてくれました。地元農家さんのにんじん、大根、キャベツを使い、他にもキムチ、豚肉、豆腐、ねぎ、ほうれん草、もやし、にら、しいたけ、しらたきとたくさんの具材が入っています。今日はとても寒かったですが、食べると体の中から温まり、とても好評でした。
今日は野菜がたくさんあるので切るのが大変ですが、いつも通り丁寧に切ってくれています。
本当に野菜タップリです!
おいしいキムチ鍋ができました。
12月20日 肉みそキャベツ丼・かぼちゃの煮物・ゆず風味の鶏塩汁・牛乳
冬至は、一年で最も昼が短く、夜が長くなる日です。日本では昔から、冬至の日にかぼちゃを食べたりゆず湯に入ったりする風習があります。かぼちゃは別名「なんきん」と呼ばれ、冬至の日に「ん」のつく食べ物を食べると「運」を呼び込めると言われています。また、ゆずには血行を良くして体を温めたり、風邪を予防したりする効果があります。今日の給食では、冬至に合わせて「かぼちゃの煮物」と、すりおろしたゆずの皮と絞った果汁で風味付けをした「ゆず風味の鶏塩汁」を作りました。冬至は12月21日なので1日早いですが、これを食べて運を呼び込み、風邪を予防できると良いですね。
大きなかぼちゃが届きました。1/4でこの大きさです。
大きさがそろうように切ります。難しいですが上手に切ってくれています。
かぼちゃは煮崩れやすいので、一度蒸してから煮汁に入れて静かに煮ます。上手く煮れました。
ゆずは地場産のものです。皮をすりおろし、果汁をしぼります。
ゆずは汁の仕上げに入れます。爽やかな香りと味が苦手な生徒もいたようですが、おいしかったと言ってくれた生徒もいました。
12月19日 ご飯・鮭の香草パン粉焼き・チキンサラダ・ミネストローネ・牛乳
香草は、特徴的な香りをもつ草や、香りの強い草のことをいい、バジルやパセリ、オレガノ、タイム、ローズマリーなど色々な種類があります。香草のもつ香りや味を利用することで、風味付けをしたり、魚や肉などの臭みを消したりして、料理をよりおいしくすることができます。今日は、バジルとパセリを混ぜたパン粉を鮭にまぶして焼きました。食べると香草の香りと風味がふわっとしてきておいしかったです。
オリーブ油、にんにく、白ワイン、塩、こしょうで漬け込んだ鮭に、バジルとパセリを混ぜたパン粉をまぶします。
パン粉がおいしそうに色付き、香草の良い香りもしています。
12月18日 ごぼう入りそぼろご飯・おでん・糸寒天の和え物・紅まどんな・牛乳
おでんは、串に刺して焼いた豆腐にみそを塗った「田楽」から生まれたと言われています。この豆腐の田楽がこんにゃくに変わり、その後、しょうゆ味で煮込むようになり、煮込みおでんと呼ばれるようになりました。
また、今日の果物の紅まどんなは、南香と天草のかけ合わせで生まれた、愛媛県オリジナルの柑橘です。ゼリーのようなとろける果肉と、ジュースのようにたっぷりの果汁が特徴で、贈り物としても人気があります。収穫時期が約1か月間と短く、今の時期にしか食べられない貴重な果物です。
おでんの具材はいくつかに分けて煮ています。こちらは大根、にんじん、ちくわ、ちくわぶを煮ています。
こんにゃくは揚げボールと一緒に煮て、うま味を少しでも染み込ませます。
うずら卵は割れないように気を付けながら落し蓋をして静かに煮ます。
がんもどきは崩れやすいので、煮汁を入れて落し蓋と蓋をしてスチームコンベクションオーブンで煮ます。
揚げボール、がんもどき、うずら卵は一人2個ずつ数えて配缶しました。
よく煮込んだら全てをバットに配缶して、軽く全体を混ぜ合わせます。
今日の果物の紅まどんなです。色も形もきれいです。
1/4にカットしました。皮が薄く、果肉たっぷりなのでお得な感じがします。
12月17日 ツナコーントースト・ガーリックシュリンプサラダ・にんじんと冬野菜のポタージュ・牛乳
今日は、めぐみちゃんメニューの第2弾で、2年B組グループが考案した「にんじんと冬野菜のポタージュ」を作りました。西東京市内の農家さんからにんじんを届けてもらいました。メインのにんじんは、よく煮てミキサーにかけてペースト状にしたものと、サイコロ状に切ったものを合わせて24kgも使っています。野菜の旨みを引き出すように煮てからなめらかなペースト状にし、味付けは塩、こしょうのみとシンプルだったので、野菜の甘みが感じられておいしかったです。
にんじんとかぶは小さなサイコロ状に切ります。
にんじんや玉ねぎ、じゃが芋はよく煮込んでからミキサーにかけます。これだけでもおいしいです。
野菜と豚ガラでとった出汁と、牛乳、生クリーム、バターを加えるとポタージュらしくなりました。
12月16日 豆ご飯・きびなごのから揚げ・ゆず香和え・きりたんぽ汁・牛乳
秋田県の代表的な郷土料理に「きりたんぽ」があります。きりたんぽは、炊いたご飯を潰して杉の木の棒に巻きつけて焼いたものです。きりたんぽの名前の由来には様々な説がありますが、やりの稽古に使う「たんぽやり」に形が似ていたことなどから名付けられたと考えられています。棒からはずして切って鍋に入れたり、棒状のままみそを塗って焼いたりして食べられますが、給食では、きりたんぽを野菜や肉と一緒に鶏ガラのだしで煮込んだ「きりたんぽ鍋」風の汁物にしました。きりたんぽはほとんど煮ていませんでしたが、食缶の中で保温されている間に柔らかくなって形が崩れてしまったのが少し残念でした。
こちらがきりたんぽです。ちゃんと焼かれているので少し香ばしさがあります。
一口サイズにカットします。
きりたんぽ鍋の大事な具材の一つである「せり」も入ります。
ごぼう、まいたけ、大根、ねぎも入り、鍋らしくなりました。
12月13日 ココアフレンチトースト・オリエンタルサラダ・手作りニョッキのクリーム煮・牛乳
ニョッキはだんご状のパスタの一種です。じゃが芋を蒸してつぶし、小麦粉やチーズを練り込んで作ります。イタリアではよく作られていて、特にローマ地方ではよく食べる習慣があります。ローマでは金曜日は肉などを食べず、軽い食事にしていたので、その前日の木曜日はしっかりお腹がいっぱいになるようにニョッキを食べることから、「木曜日はニョッキの日」という言葉もあるそうです。給食ではクリームソースで煮込みましたが、バターやチーズをかけて食べたり、ミートソースで和えて食べてもおいしいです。
ニョッキ作りは、まずじゃが芋を蒸してなめらかにつぶすところからスタートです。
強力粉、脱脂粉乳、バター、粉チーズを混ぜ合わせ、よくこねます。
まとまりました。少しねかせます。
棒状に細く伸ばします。
1.5cmほどの幅に切ります。
フォークの背で一つずつ筋目を付けます。このひと手間でソースがより絡みやすくなります。
たっぷりのお湯でゆでれば、もちもちのニョッキが完成です。
クリームソースがしっかり絡みました。
12月12日 こぎつねご飯・いかのさらさ揚げ・白菜のおひたし・豚汁・牛乳
白菜は中国で生まれた野菜で、約130年前に戦争に行った日本人が中国から種を持ち帰ったことから、日本で栽培されるようになりました。白菜はほとんどが水分ですが、風邪予防や免疫力アップに効果のあるビタミンCや、お腹の調子を整え、美肌作りに効果も期待できる食物繊維を多く含みます。給食では、今が旬の白菜をおひたしにしました。
12月11日 サイコロポークピラフ・ジャーマンポテト・ABCスープ・飲むヨーグルト
ジャーマンポテトは、ベーコンと玉ねぎをバターや油で炒め、そこに食べやすい大きさに切ったじゃが芋を加え、塩・こしょうで味付けした料理です。給食では、じゃが芋を揚げてから炒めた具材と合わせています。好評だったようで、完食のクラスも多かったです。
じゃが芋はカリッとなるように素揚げします。
ベーコンと玉ねぎは炒めて味付けもしておきます。
揚げたじゃが芋と炒めた具材を混ぜ合わせたら完成です。
12月10日 ご飯・元気みそ・里芋コロッケ・むらくも汁・牛乳
むらくも汁は、溶いて流し入れた卵が汁の中に薄い膜のように広がり、それが空にうっすらとたなびく「むら雲」のように見えることからその名前がついています。むら雲は高積雲の一種で、「まだら雲」や「ひつじ雲」とも呼ばれています。卵がふわふわに仕上がるように、水溶き片栗粉で汁にとろみをつけるのがポイントです。また、とろみがついているので冷めにくく、体が温まるので寒い季節にはぴったりの汁物です。
里芋は蒸してなめらかになるように潰します。
炒めた具材と芋を合わせ、小判型に形を整えて衣を付けます。
油でカラッと揚げます。中はとろっとしています。
むら雲のようにふわっと卵が広がりました。
12月9日 冬野菜カレーライス・クルートサラダ・フルーツポンチ・牛乳
冬は、寒さや乾燥、雪など、人間だけでなく作物にとっても厳しい季節ですが、より一層おいしくなる野菜もあります。ほうれん草や白菜などの葉物野菜は、寒さで凍ってしまわないように水分を減らして糖分を増すので、甘みも栄養も増します。にんじんや大根などの根菜類は、寒くなると成長が遅くなり、土の中の栄養をたくさん蓄えられるようになります。冬に採れる野菜には、体を温める効果があったり、風邪の予防に役立つビタミンAやCを含んでいるものが多く、寒い冬を元気に乗り切るのに効果的です。今週は市内小中学校一斉の残菜調査週間ということもあり、どの料理も残菜がとても少なかったです。全て完食のクラスもありました。
今日れんこんは薄めに切ってシャキシャキ感が残るようなタイミングで入れます。
ブロッコリーとカリフラワーはゆでて最後に混ぜ合わせました。
12月6日 カリカリ梅ご飯・ぶりのみぞれ和え・野菜の香味和え・ふぶき汁・牛乳
明日、12月7日は「立春」や「冬至」といった二十四節気の一つ、「大雪(たいせつ)」です。「大雪」は、季節を表す言葉で、本格的に冬が到来する時期を表しています。今日の給食は、この「大雪」にちなんで、「みぞれ」や「ふぶき」といった「雪」を表す言葉がついた料理になっています。「ブリ」は冬になると脂がのってうま味も強くなるため、「寒ブリ」と呼ばれとても人気があります。今日は長崎県産のブリをから揚げにして、大根おろしで作ったたれと絡めています。大根おろしの見た目がみぞれに似ていることからみぞれ和えと呼んでいます。ふぶき汁は、豆腐を細かくほぐし、ふぶきを表現しています。
今日は角切りのブリに下味をつけて揚げます。脂がのっているのがわかります。
大根おろしは調味料と一緒に加熱してみぞれソースを作り、揚げたブリと絡めます。
ふぶき汁の豆腐は手で細かくほぐします。
吹雪に見えるでしょうか。今日は雪だるまの形をしたかまぼこも入っています。
12月5日 コーンライス・生揚げのチーズ焼き・小松菜ときのこのスープ・牛乳
今日の給食は、西東京市内の小中学校共通の体力向上メニューです。1学期は「鉄分強化」がテーマでしたが、2学期は「カルシウム強化」がテーマの献立になっています。カルシウムは体内で作ることができない栄養素なので、食事で摂る必要があります。将来のために、今のうちにカルシウムをしっかり摂って骨量を増やしておきたいですね。今日の給食は、カルシウム豊富な生揚げ、チーズ、小松菜などを取り入れましたが、みんなしっかり食べてくれていました。
食べやすいように小さめのサイコロ状に切った生揚げを、みそが入った和風ミートソースに合わせます。
カップに入れて、チーズとパセリをかけてオーブンで焼きます。
グラタン風のおいしそうな焼き上がりです。
12月4日 肉汁うどん・ごま和え・めぐみちゃん蒸しパン・牛乳
西東京市の産業振興課では、地産地消を推進する「めぐみちゃんメニュー事業」を行っていて、その一環で、1学期に市内産農産物を使用したメニューを募集していました。ひばりが丘中学校からは、2年生グループが考えたメニュー6つと1年生グループが考えたメニュー1つの合計7つのメニューが選ばれ、市内の飲食店で期間限定で販売されています。残念ながら商品化されなかったメニューの中にも素晴らしいものがたくさんあったので、給食でも少しアレンジして3つのメニューを作ることにしました。今日は、2年A組のグループが考えた「めぐみちゃん蒸しパン」です。市内産の小松菜とゆずを生地に練り込み、さつま芋は上にトッピングしました。小松菜もゆずも味の主張があまりない仕上がりだったので、苦手な人でも食べられたと思います。さつま芋と一緒に食べると甘さがちょうど良く、おいしかったです。
小松菜はゆでてからミキサーにかけて細かくします。
ゆずは皮をすりおろして果汁をしぼり、生地に混ぜます。
さつま芋は角切りにして上に乗せました。
きれいな黄緑色の蒸しパンが出来上がりました。さつま芋の色も映えてきれいです。
12月3日 ジャンバラヤ・チョップドサラダ・シーフードチャウダー・みかん・牛乳
今日は、アメリカの料理です。「ジャンバラヤ」はアメリカ南部のルイジアナ州の料理で、スペイン料理のパエリアをもとに作られた、スパイシーな炊き込みご飯です。大きな鍋で作って大人数で食べることが多く、今ではバーベキューと同じくらいアウトドアパーティーの定番メニューとなっています。「チョップドサラダ」は、食材を細かく切ったニューヨーク生まれのサラダです。「チャウダー」は、野菜や魚介類を煮込んだスープで、代表的なのはアサリなどの二枚貝を入れたクラムチャウダーですが、給食ではホタテ、いか、えびを入れた魚介のチャウダーにしました。
今日はさいの目切りのものが多いので、ほとんどの野菜が手切りです。
給食のジャンバラヤは、カレー粉やパプリカパウダー、トマトペーストなどを具材に加えて炒めています。
具材ができたらご飯とよく混ぜ合わせます。
チョップドサラダはどの野菜も同じような大きさに切り揃えられて、彩りもきれいです。
ベビーホタテ、いか、えびは下ゆでをして白ワインを振っておきます。
スープとシチューの間くらいのとろみがつくように仕上げました。
12月2日 ご飯・さばのカレー風味焼き・おかか和え・かす汁・牛乳
かす汁は、日本酒をしぼった時にできる「酒かす」を入れた汁物です。酒かすには、たんぱく質やビタミン、ミネラルなどが豊富に含まれています。甘酒を作ったり、肉や魚を漬け込んで焼いたり、漬物にしたり、スイーツを作ったりするときにも使われます。酒かすを食べると血管が拡張して血行が良くなり、体が温まるので、かす汁は寒い時期にぴったりの汁物です。酒かすの味は生徒の口に合うか不安でしたが、おかわりしている生徒もいて、残食も少なめで良かったです。
酒かすは出汁で溶いてから、調理の終盤に入れます。
野菜もたくさん入って栄養満点で、体が温まります。