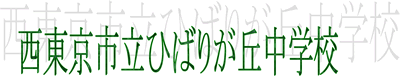11月の給食
更新日:2024年11月29日
毎日の給食
11月29日 きな粉揚げパン・かぶのサラダ・キャベツのミートボールスープ・牛乳
今日は、西東京市内の保育園・小学校・中学校の共通献立です。日にちは違いますが、11月または12月に提供されます。メニューは「キャベツのミートボールスープ」で、なるべく西東京市内で採れた野菜を使って作ります。ひばりが丘中学校では、キャベツと小松菜をいつもお世話になっている農家さんに届けていただきました。野菜がたっぷり食べられるスープになりました。
ミートボールを一つ一つ丸めてスープに入れます。
キャベツは大きなザルに山盛り2個分も使います。
小松菜も収穫してすぐに届けてくれるので新鮮です。
あふれそうなくらい野菜もミートボールもたっぷり入っています。
11月28日 あんかけ丼・たこと野菜のレモン風味・みかん・牛乳
みかんやオレンジなどのかんきつ類と呼ばれる果物は、インドや東南アジアで生まれたといわれ、世界中に100種類以上もあります。皮がやわらかく簡単に手でむけるものを総称してみかんと呼びますが、温州みかん、夏みかん、いよかんなどは日本独自の品種です。ビタミンCやクエン酸が豊富に含まれ、疲労回復や風邪の予防・回復に効果があり、肌の調子を整えるのにもおすすめです。今日のみかんは、西東京市内の農園から届けてもらいました。大きなみかんで、甘味と酸味のバランスがよくおいしかったです。
色も形もきれいです。もちろん味もおいしいです。
11月27日 ご飯・ヤンニョムチキン・チョレギサラダ・トッポギ入りスープ・牛乳
今日の給食は、韓国の料理です。「ヤンニョムチキン」は韓国風のフライドチキンで、コチュジャン入りの甘辛いタレをからめます。「チョレギサラダ」は、実は日本人が考えた韓国風の料理です。日本の食品メーカーが、ごま油ベースの塩味のドレッシングをチョレギサラダという名前で販売したことがきっかけで広まったそうです。「トッポギ」の「トッ」は餅、「ポギ」は「炒め」を意味します。棒状の形が特徴で、甘辛いタレで炒めて食べます。給食では、トッポギ用のお餅をスープに入れました。韓国料理は生徒に人気があるので、今日は残食がとても少なかったです。特にヤンニョムチキンはほぼ完食でした。
鶏肉はカラッと揚げます。
甘辛いタレをたっぷり絡めます。
チョレギサラダはのりとごまがしんなりしないように盛り付けました。
トッポギはスープに入れても溶けず、もちもちでおいしいです。
11月26日 きのこご飯・ししゃものさざれ焼き・たまごと青菜の炒め物・ごまだれ汁・牛乳
今日のきのこご飯には、「しめじ、しいたけ、まいたけ、えのきたけ、ひらたけ」が入っています。しめじは地面を占領するほど一面に生えることや湿気の多い所に生えること、しいたけは椎の枯れ木、えのきは榎の木にそれぞれ発生していたこと、まいたけは昔から「幻のきのこ」と呼ばれるほど希少価値があり、見つけた人が舞い上がって喜ぶこと、ひらたけは、名前のとおり平たく見えることからそれぞれ名付けられています。また、ししゃものさざれ焼きの「さざれ」とは「細かい、小さい」という意味で、細かいパン粉をつけて焼くことからこの名前が付いています。天板に接している面がしっとりしてしまったので、次回はもう少しカリッとなるようにしたいです。今日は、しいたけ、ひらたけ、キャベツ、小松菜、白菜、ほうれん草と、地場産の野菜をたくさん使わせていただくことができました。
給食では干ししいたけを使うことがほとんどですが、今日は生しいたけです。肉厚でおいしそうです。
こちらはひらたけです。地元農家さんが持って来てくれました。
きのこは炒め煮にして、旨味を引き出します。これを酒としょうゆを入れて炊いたご飯に混ぜ合わせます。
ししゃものさざれ焼きは、酒をふっておいたししゃもにマヨネーズを絡めます。
パン粉をしっかりとまぶしてオーブンで焼きます。
火が通って焼き色が付くまで焼いたら完成です。
11月25日 カツカレー・花野菜のサラダ・りんご(サンふじ)・牛乳
今日は、読書月間コラボメニューの第3弾で、「アンソロジー カレーライス!!」という本に出てくる「カツカレー」を作りました。この本は、こだわりの食べ方や調理法、カレーにまつわる思い出話、これまでに食べた忘れられないカレーなどを、33人の作家や著名人がつづったエッセイ集です。カツカレーは、五木寛之さんの「カツカレーの春」という話の中に出てきます。今日はトンカツではなくチキンカツでしたが、給食で提供されることの少ないカツカレーに生徒はとても嬉しそうでした。
下味をした鶏肉に、丁寧に衣を付けます。
サクサクジューシーに揚がりました。
今日のカレーの野菜は玉ねぎ、セロリ、にんじんだけです。玉ねぎはよく炒めます。
今日はいつもより少しさらっとした仕上がりです。
11月22日 ご飯・さんまの竜田揚げ・おひたし・塩豚汁・牛乳
11月24日は、“いい日本食”の語呂合わせから、「和食の日」となっています。日本の秋は「実り」の季節であり、自然に感謝し、来年の五穀豊穣を祈る祭りなどの行事が全国で盛んに行われる季節でもあります。日本の食文化にとって大切な時期である秋の日に、毎年、一人ひとりが和食文化について認識を深め、和食文化の大切さを再認識するきっかけの人なっていくよう願いをこめて、和食の日が制定されました。今日は、24日よりも少し早いですが、旬の食材を使い、ご飯を中心としてバランスよく食べられる和食の献立になっています。和食に欠かせない「出汁」の旨味なども感じられるように仕上げました。
魚が苦手な人も少しは食べてみようと思えるように、短冊切りにした秋刀魚を使いました。
下味をつけて、片栗粉をまぶして揚げました。大きさも味も食べやすいです。
11月21日 ジャージャー麺・野菜の中華和え・焼き芋・牛乳
焼き芋と言えば甘くておいしいですが、ただ焼いたりふかしたりしただけのさつま芋より甘いのはなぜでしょうか?さつま芋の主な成分であるでんぷんは、あまり甘くないのですが、温められるとさつま芋に含まれる「酵素」が働き始め、でんぷんを甘みに変えてくれます。この酵素が活発に働く温度が70℃位で、この温度でじっくりと温めると、甘くておいしい焼き芋ができます。給食室では、1時間じっくりと蒸して甘みを出した後、温度を変えながら30分焼いて少し香ばしく仕上げました。今日は、焼き芋にするとおいいしい「鳴門金時」と「紅はるか」で作りました。
皮ごと食べられるように、1本1本きれいに洗います。
オーブンで焼いてから半分に切って提供しました。
断面はこのようになっています。しっとりおいしくできました。
11月20日 かやくご飯・ちくわの二色揚げ・かぶの甘酢和え・すまし汁・牛乳
かぶは一年中流通していますが、11月から1月頃の寒い時期は甘みが増して特においしくなります。かぶの歴史は深く、日本には弥生時代に伝わったと言われ、「日本書紀」に持統天皇がかぶの栽培を推奨するおふれを出したという記録が残されているそうです。かぶの白い根の部分には、でんぷんを分解する消化酵素のアミラーゼが多く含まれているので、胃もたれや胸焼けを解消する働きや、整腸効果があります。また、葉っぱも栄養豊富なので、捨てるのはもったいないです。今日は葉っぱも一緒に和え物に使いました。
今日のちくわは二色揚げです。一つは衣に青のりを入れました。
もう一つはゆかりを混ぜました。
二色並べるときれいです。とても寒い日でしたが、なんとなく春を感じさせる色合いでした。
11月19日 オムライス・ポテトサラダ・コンソメスープ・牛乳
今日は、読書月間コラボメニューの第2弾で、瀬尾まいこさんが書いた「掬(すく)えば手には」という本に出てくる「オムライス」を作りました。この本の中で、このお店のオムライスがとてもおいしそうに表現されています。お店のオムライスはソースがかかっていますが、店主が子供の頃におばあちゃんが作ってくれたオムライスの卵にはケチャップで絵が描いてあったとも書かれていたので、今日はケチャップも付けました。絵や字を書いて楽しんでいる生徒も見られました。
チキンライスは具だくさんです。
オムライスの卵は420個も使っています。
天板に薄く卵液を流してオーブンで蒸し焼きにします。
焼き上がったら人数分にカットします。
11月18日 ご飯・和風ハンバーグ・からし和え・僧兵汁・牛乳
僧兵汁は、三重県の郷土料理です。三重県北部の菰野町(こものちょう)にある湯の山温泉に、三岳寺(さんがくじ)というお寺があります。戦国時代に織田信長が攻めてきた時、三岳寺の修行僧が、僧兵となって戦いました。修行僧は普通、肉を食べない決まりですが、戦うためにイノシシやシカ、ヤマドリなどの肉と季節の野菜を入れたみそ仕立ての鍋物を食べて、スタミナをつけたとされています。現在でも旅館や地元のお祭りなどで食べられているそうです。給食では、鶏肉と季節の野菜をたくさん入れて作りました。にんにくも少し入れたので、いつものみそ汁とはまた違う風味があっておいしかったです。
今日のハンバーグは和風です。肉だねには豆腐やひじきを混ぜ込みました。
ソースは大根おろしのソースなのでさっぱりとした仕上がりです。
僧兵汁にはヤマドリをイメージして鶏肉を入れました。
具だくさんで栄養たっぷり。体も温まります。
11月15日 フィッシュバーガー・ピクルス風サラダ・豆乳コーンチャウダー・ジョア(プレーン)
今日のフィッシュバーガーの魚は「モウカサメ」です。モウカサメはとても大きくて、全長が最大で3m、体重は170kgくらいあります。サメの水揚げは、宮城県の気仙沼が9割を占めていて、今日のサメも宮城県で水揚げされたものです。宮城県ではモウカサメと呼ばれていますが、体の色や目、口、頭の形がネズミに似ていることから、東京では「ネズミザメ」とも呼ばれています。魚料理はいつもやや残食が多いですが、今日のフィッシュバーガーはとても残食が少なかったです。
サメのフライはソースにくぐらせてから挟みます。
おいしそうにできました。見た目よりも満足感があるバーガーです。
11月14日 ぶたばら飯・中華野菜スープ・おかしな目玉焼き・牛乳
11月は読書月間です。給食では、読書部の皆さんが推薦してくれた本に出てくる料理を提供します。今日は、小川糸さんが書いた「あつあつを召し上がれ」という本に出てくる「ぶたばら飯」を作りました。白いご飯の上に煮込んだぶたばらと熱い葛あん、色を添える程度の小松菜が大きなどんぶりに山盛りになっているという様な表現があったので、なるべく近づけられるように作りました。お肉は軟らかくなるようにじっくり1時間以上煮込んでいます。初めて作りましたが、とても好評だったようでほとんど残食がありませんでした。ぜひ本も読んでみてほしいです。
豚ばら肉は、一度さっとゆでて余分な脂を落とします。
さっと炒めて少し焼き色を付けます。
アクや余分な脂を取りながら丁寧に煮込みます。
調味料で味付けし、お肉がやわらかくなったら小松菜を入れて、全体にとろみをつけたら完成です。
11月8日 きのこクリームスパゲティ・もやしのシャキシャキサラダ・さつま芋チップス・牛乳
今日、11月8日は、語呂合わせから「いい歯の日」になっています。健康な歯を保つためには、「よく噛んで食べること」「食べたらしっかり歯を磨くこと」「カルシウムを多く含む食べ物をとること」「間食は時間や量を決めて食べること」「甘いものをとり過ぎないこと」などが大切です。よく噛んで食べると、唾液がたくさん出て虫歯や歯周病を予防したり、食べ物の消化吸収が良くなったり、脳が活性化されて記憶力がアップしたりなどの良い効果が得られます。今日は、全体的に噛み応えのある食材やカルシウムを多く含む食材を多く取り入れ、いつもより歯応えがあるような給食でしたが、しっかり噛んでほとんど残さず食べてくれていました。
しめじ、エリンギ、マッシュルームを使った旨味たっぷりのクリームソースです。
さつま芋はパリパリになるまで低温でじっくりと揚げます。
粗熱を取ったら粉糖を全体にまぶします。
バットに配缶してから最後に粉糖をもうひとかけして見た目もきれいに仕上げました。
11月7日 ご飯・鮭の焼き漬け・きりざい・スキー汁
今日は「新潟県」の料理です。今日のご飯は、新潟県の農家さんから届けてもらったコシヒカリの新米です。コシヒカリはつやつやとしていてねばりや弾力があり、甘みが強いのが特徴です。「鮭の焼き漬け」は、鮭を焼いてからたれに漬け込む料理で、冷凍技術が発達していなかった江戸時代から保存食として作られていたそうです。「きりざい」の「きり」は切ること、「ざい」は野菜を表し、細かく切った野菜と、納豆や漬物を混ぜ合わせます。「スキー汁」は、明治時代にスキーが伝えられた時に生まれました。大根とにんじんはスキー板、豆腐は雪、長ねぎとごぼうは雪道を歩くときに履く“かんじき”、こんにゃくはスキーの滑った跡、しいたけは“みの”や笠をそれぞれ表しています。また、さつま芋が入るのも特徴です。今日はスキー汁のさつま芋とにんじんも、新潟県の農家さんから直送してもらいました。
コシヒカリの新米ご飯。ふっくらつやつやです。
鮭は焼いてからたれに漬け込みます。
きりざいの野菜は細かく刻みます。
刻んだ野菜と納豆、たくあん漬け、ごまが合わさって食感も良いです。
さつま芋も新潟県産です。短冊切りにして入れます。
様々な意味が込められた具材がたっぷり入った汁物です。体も温まります。
じゃこ菜飯・揚げ出し豆腐・海藻の和え物・五目汁・牛乳
揚げ出し豆腐は、豆腐にでん粉や小麦粉などをまぶして油で揚げ、しょうゆやみりんで味付けしただし汁をかけた料理です。ねぎや大根おろしなどの薬味をかけることもあります。今日は、豆腐に小麦粉とコーンスターチを混ぜたものをまぶして揚げました。コーンスターチは名前の通りとうもろこしからできています。和食や中華料理のとろみ付けには片栗粉を使いますが、コーンスターチは西洋料理のソースやスープ、カスタードクリームなどのとろみ付けによく使われます。揚げ物の衣にコーンスターチを使うと、カリッとしておいしいです。
よく水気を切った豆腐に、小麦粉とコーンスターチを混ぜたものをまぶします。
衣がカリッと軽い感じに揚がりました。
手作りのたれと糸削り節をたっぷりとかけたら、食べる頃には味がよくしみた揚げ出し豆腐の完成です。
11月1日 シナモンアップルトースト・ハーブチキンサラダ・チリコンカン・牛乳
シナモンは香辛料のひとつで、クスノキ科の木の皮を乾燥させたものです。ほのかな甘みを感じさせる独特の香りとかすかな辛みをもつシナモンは、世界でも最も古くから知られているスパイスで、スパイスの王様とも呼ばれています。甘いものとの相性がとてもよく、パイやクッキー、パンなどのお菓子類や、紅茶やコーヒーなどのドリンク類の香りづけによく使われ、特にりんごとの相性は抜群です。今日は、りんごとりんごジャム、はちみつ、マーガリン、シナモンを混ぜ合わせてパンに塗ってトーストにしました。生徒のおかわりじゃんけんも盛り上がっていました。
今日はりんごを皮ごと使いました。りんごだけで煮てからジャムやシナモンと混ぜ合わせます。
パンの端までしっかり塗ります。
少し焼き色がついて、おいしそうに焼けました。