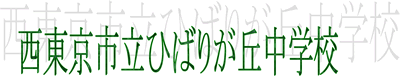5月の給食
更新日:2024年5月31日
毎日の給食
5月31日 スタミナキムチ丼・小松菜とひじきのサラダ・白玉入りフルーツポンチ・牛乳
明日は運動会ということで、今日の給食はスタミナアップメニューです。スタミナキムチ丼にたくさん入っている豚肉には、炭水化物などの糖質をエネルギーに変えたり、疲労回復させるビタミンB1が多く含まれています。ビタミンB1は、にんにくやニラ、ねぎ、玉ねぎなどと一緒に食べると体に取り込まれやすくなるので、今日はこれらの食材と一緒に炒めました。食欲増進効果のあるキムチもたくさん入っていて、暑さや疲れであまり元気がない人も食べやすいです。また、運動などで一気に大量の汗をかくと、汗と一緒に鉄分が体外に流れ出てしまい、鉄分不足になることもあります。サラダに入っているひじきや小松菜には、鉄分が多く含まれているので、サラダもしっかり食べましょう。そして、試合などの前日にはエネルギー源となる炭水化物を多く摂ると良いです。今日はデザートに白玉団子入りのフルーツポンチを作りましたが、生徒たちは大喜びでした。家では十分休養をとって、明日の運動会は全力で頑張ってほしいと思います。
肉も野菜もたっぷり入っています。香りをかぐだけで元気が出てきます。
ひじきと小松菜だけでなく、にんじんや大根、コーンも入って彩りきれいです。
白玉団子は手作りです。豆腐が入っているので栄養価も高く、時間が経っても硬くなりにくいです。
5月30日 梅ひじきご飯・卯の花コロッケ・こんにゃくの和え物・沢煮碗・牛乳
「卯の花」とは初夏の5月から6月頃に咲く「ウツギ」という木の花のことです。卯の花の小さな白い花が集まる様子がおからと似ていることから、おからは卯の花ともいわれるようになりました。旧暦の4月のことをいう「卯月」もこの卯の花が由来で、「卯の花が咲く月」であることから名付けられました。おからは豆乳を作る時に出るしぼりかすですが、豆乳よりも食物繊維やたんぱく質が多く含まれています。給食ではおからのパサパサ感が苦手な人でも食べやすいようにコロッケにしました。運動会の予行で疲れている生徒も多かったようですが、コロッケはほぼ完食でした。
今日のコロッケはおからがたくさん入ります。遠目から見るとなんとなく卯の花に似ている気もします。
ひき肉と玉ねぎを炒め、蒸してつぶしたじゃが芋とおからをよく混ぜ合わせます。
きれいな小判型に成型して、衣をつけて揚げます。
破裂しないように気を付けながらじっくり揚げます。ほとんど破裂することなく、上手く揚げられました。
5月29日 カラフルピラフ・チキングラタン・ミネストローネ・ジョア(マスカット)
ミネストローネはイタリア語で「具だくさんのスープ」という意味があります。イタリアの家庭でよく食べられているスープで、日本にとってのみそ汁のようなものです。ミネストローネの多くはトマト味ですが、地域によって使う野菜や味付けが違います。給食ではウィンナーやにんじん、玉ねぎ、セロリ、マカロニなどを入れたトマト味のミネストローネを作りました。さっぱりしていて暑い日でも飲みやすかったです。
グラタンのじゃが芋は、せん切りにして蒸してから合わせています。
カップに均等に入れます。
チーズ、パン粉、パセリを散らしてオーブンで焼きます。
チーズがとろけ、焼き色が付いたら完成です。
5月28日 みそラーメン・春巻き・華風きゅうり・牛乳
みそラーメンの発祥は、1955年の北海道の札幌です。「味の三平」というお店の店主が、みそ汁をヒントに工夫を重ねて「みそ味メン」を生み出し、それがいつしか「みそラーメン」という名前になったそうです。ラーメンは寒い日に食べるとおいしいですが、今日みたいな蒸し暑い日にも食べやすくておいしかったです。今日のメニューは大人気で、残食もとても少なかったです。
給食のラーメンは野菜もたっぷり入っています。あっさりしていてスープも飲みやすいです。
春巻きは中の具から手作りです。600個、一つ一つ丁寧に包みます。
皮がパリパリに揚がりました。中は具がたっぷりです。
5月27日 ご飯・さわらの辛味焼き・納豆和え・かきたま汁・牛乳
納豆は大豆が発酵してできたものですが、この発酵を促すのに欠かせないのが納豆菌です。煮た豆に納豆菌をかけて人肌くらいに温めると、納豆菌はどんどん増え、ネバネバや香りのもととなる成分を作り出し、納豆が出来上がります。その時に、アミノ酸などの旨味のもとになる成分や、ビタミンK2、ナットウキナーゼといった大豆にはない栄養も作り出し、栄養たっぷりになります。今日の和え物は、ひきわり納豆に野菜やかつおぶしを合わせました。ご飯にかけて食べてもおいしいです。
納豆は調味液と合わせておいてから野菜と和えました。かつお節も入っていて納豆が苦手な人でも食べやすい味になっています。
5月24日 チキンカレーライス・ほうれん草のサラダ・メロン・牛乳
メロンは大きくなる途中で表皮の成長が止まってしまいますが、内側の果肉はその後も成長していきます。その時に起きる表皮のひび割れがメロンの特徴的な網目模様で、きれいな網目模様が出ているものほどおいしいと言われています。今日は、茨城県産の「アンデスメロン」です。アンデスメロンは害虫がつきにくくて栽培しやすいことから、「作って安心」「売って安心」「買って安心」という3つの安心があり、「安心ですメロン」という名前で売り出される予定でした。しかし、名前にセンスがないことと、メロンは芯を取って食べることから、名前からも「しん」を取って「アンデスメロン」となったそうです。香りがとても良く、甘くてちょうど食べごろのメロンでした。
今日のメロンは大きいです。切る前から良い香りがしています。
種は給食室で残さずきれいに取っています。
1/16に切って提供しましたが、それでもしっかりとした大きさでした。
5月23日 五目ご飯・高野豆腐の卵焼き・磯香和え・みそけんちん汁・牛乳
高野豆腐は、今から約800年前に考えられたと言われ、高野山で最初に作られたので高野豆腐という名前になったそうです。生の豆腐を凍らせて低温で熟成させ、水分を抜いて乾燥させて作られているので、凍り豆腐とも呼ばれます。日本に昔から伝わる保存食で、たんぱく質やカルシウム、鉄分などが豊富です。今日は、高野豆腐を鶏ひき肉やにんじんと一緒に炒め煮にしておいしい味をしっかり吸わせ、卵焼きの具材にしました。しっとりふんわりした仕上がりで、ボリュームがありましたが多くの生徒が完食でした。
高野豆腐にしっかりと味を吸わせます。
卵液とよく混ぜ合わせます。
今日はカップに入れて焼きます。具材と卵液がなるべく均等にいきわたるように入れます。
ふんわりとふくらみ、おいしそうに焼けました。
5月22日 セサミトースト・アスパラ入りグリーンサラダ・ポークビーンズ・牛乳
アスパラガスは、4月から6月中旬の春の時期に旬を迎えます。アスパラガスという名前は、ギリシャ語で「新芽」を意味する言葉から付けられていて、その言葉どおり、私たちが普段食べているのは葉っぱや枝が出る前の、土の中から出たばかりの若い芽と茎の部分です。一般的に食べることが多いのはグリーンアスパラガスですが、ホワイトアスパラガスという白いアスパラガスもあります。この二つの品種は同じですが、日光によく当てて光合成させるとグリーンになり、芽が出る前に土をかぶせて日光が当たらないようにすると白くなります。最近では、品種の違う紫色のアスパラガスも栽培されています。今日は薄くスライスしてサラダにしました。シャキシャキしていておいしかったです。
みずみずしいアスパラガス。シャキシャキ感が残るようにさっとゆでました。
5月21日 ご飯・手作りふりかけ・肉じゃが・野菜炒め・牛乳
ふりかけは、お米を主食とする日本独自の食文化です。ふりかけを考案したのは熊本県の薬剤師さんだと言われています。大正時代初期、当時の日本では食糧難によるカルシウム不足が問題となっており、魚を骨ごと粉にして食べることでカルシウム不足を解消しようとしました。魚が苦手な人でも食べやすいようにごまや青のりを加えて味付けし、それをご飯に乗せて食べたのがふりかけの始まりです。今日は、じゃこ、ごま、かつおぶし、青のりを入れた、手作りのふりかけです。じゃこをしっかり焼いたので、カリカリで食べやすかったです。
水分がなくなりパラパラになるまで、焦がさないようにじっくり煎ります。
5月20日 麻婆豆腐丼・チンゲン菜の中華スープ・デコポン・牛乳
麻婆豆腐は、100年ほど前に中国四川省の都、成都に住んでいるチャオチャオという女性が生み出した料理だそうです。料理がとても上手なチャオチャオの家の両隣りが豆腐屋と羊肉屋で、その材料で作ったのが麻婆豆腐でした。本場のものは唐辛子をたくさん使い、器に盛ってから「花椒(ホアジャオ)」という強い辛味としびれが特徴的な中国の香辛料をたっぷりかけて食べるそうです。やけどするほど熱々の状態で食べるので、唐辛子の辛味や花椒のしびれる味がより際立ちますが、豆腐の甘みも感じられるので、四川料理の中でも人気のある料理です。辛いのが苦手という人もいるので、給食では辛みは抑え、旨味のある麻婆豆腐にしています。
5月17日 ご飯・かつおの竜田揚げ・たこもみうり・吉野汁・牛乳
今日は3年生が修学旅行で行く奈良県の料理です。竜田揚げの「竜田」は、奈良県にある紅葉の名所「竜田川」からきています。しょうゆなどで下味をつけ、片栗粉をまぶして油で揚げると赤茶色に揚がり、ところどころに片栗粉の白色の部分ができるその見た目を、紅葉と側を流れる竜田川に見立てて名付けられたそうです。「たこもみうり」は、小口切りにしたきゅうりをやわらかくなるまでよくもみ、たこと和えた酢の物です。「吉野汁」は、奈良県の吉野地方で食べられている料理です。桜の名所としても知られている吉野山は「葛」の産地で、葛の根から葛粉を作っています。これを「吉野葛」と言い、この葛粉を使った料理には「吉野」という名前が付けられています。昔はたくさんとれた葛粉ですが、今はとても貴重です。また、今日の吉野汁にはそうめんが入っていますが、奈良県は手延べそうめんの産地の一つとしても有名です。奈良時代から作られている伝統あるそうめんは、「三輪そうめん」という名前で一つのブランドになっています。吉野汁は特に人気があったようで、残食が少なかったです。3年生は日曜日から修学旅行ですが、充実した3日間を過ごしてきてほしいと思います。
今日は角切りのかつおです。下味をつけたかつおに片栗粉をまぶして油で揚げます。
この見た目が竜田川に似ているそうです。
きゅうり、わかめ、たこを甘酢とすりごまで和えます。今日のたこはとても細かかったです。
吉野汁は、鶏肉に片栗粉をまぶして汁に入れます。
そうめんは下ゆでし、水で締めてから仕上げに入れます。
鶏肉にまぶした片栗粉で、汁全体にとろみがついています。
5月16日 オリエンタルスパゲティ・ハーブチキンサラダ・オレンジスフレ・牛乳
「スフレ」とはフランス語で「ふくらんだ」という意味で、卵白を泡立てたメレンゲに様々な材料を混ぜ合わせて作る、軽くてふんわりとした料理です。17世紀にフランスのお菓子職人が、卵白と砂糖を混ぜて焼くとパンのようにふくらむことを発見したのがスフレの始まりだと言われています。日本ではスフレというとスイーツのイメージが強いですが、フランスでは野菜や魚、チーズなどを加えて焼き上げたおかず系のスフレも一般的です。給食では、みかん缶やクリームチーズを入れたオレンジスフレを作りました。ひばり中で初めて作りましたが好評でした!
みかん缶やクリームチーズ、卵をミキサーにかけ、最後に小麦粉をさっくりと混ぜ合わせます。
カップに流し入れてオーブンで焼きます。
オーブンで焼いている間はふんわりと膨らんでいました。
5月15日 ばら寿司・大根と厚揚げの炊いたん・湯葉入り京風みそ汁・牛乳
今日は、3年生が19日の日曜日から修学旅行で行く京都府の料理です。「ばら寿司」は、すし飯の上にさばの水煮で作ったそぼろと、たまご、紅しょうがなどを彩りよく散らした、見た目が華やかなご飯です。「大根と厚揚げの炊いたん」は、京都のおばんざいの代表的な煮物です。おばんざいとは、京都の一般的な家庭で作られる日常的なお惣菜のことです。炊いたんは、「炊いたもの、煮たもの」を意味する言葉です。京都の味にならい、出汁を利かせて薄口しょうゆで仕上げました。みそ汁には京都の名物である湯葉が入っていて、京都でよく使われている西京みそで味付けしました。西京みそは塩分が少なめで、まろやかで甘みがあります。日頃食べなれないものばかりだったので残食は少し多かったですが、日本国内でも地方によって食文化が違うということを体感してもらう機会になったと思います。17日には、修学旅行でのもう一つの行き先である奈良県の料理を作ります。
すし酢と具材を混ぜたすし飯をバットに敷き詰めます。
すし飯の上に、さばのそぼろ、入り卵を順に盛り付けます。
細切りにしたかまぼこ、さやえんどうを彩りよく散らします。
最後に紅しょうがを散らしたら、彩りがとてもきれいなばら寿司の完成です。
大根はしたゆで、生揚げは油抜きをしてからじっくりと炊いていきます。
水菜は色がきれいなまま提供できるように、配缶後に散らしました。
みそ汁には湯葉が入ります。煮込んでも意外と崩れないしっかりとした湯葉です。
西京みそで味付けしているので、色もいつもより白っぽい仕上がりです。
5月13日 ターメリックライスクリームソースがけ・カラフルサラダ・マンダリンオレンジ・牛乳
マンダリンオレンジは、温州みかんにキングマンダリンを交配させてできたかんきつです。オレンジという名前ではありますがみかんの仲間で、温州みかんとほとんど同じ栄養をもち、皮がデコボコしているのが特徴です。かんきつはたくさん種類がありますが、その中でも木に実っている期間が最も長い品種です。みかんと同じように中の薄い皮も食べられます。
皮は確かにデコボコしています。あまり大きくないですが、皮が薄いので食べられる部分が多いです。
5月10日 ご飯・いかのさらさ揚げ・豚しゃぶ和え・若竹汁・牛乳
若竹汁は、春先の新わかめと春が旬のたけのこを使ったすまし汁です。わかめは塩漬けにしたり乾燥させることで一年中いつでも食べることができますが、春先の新わかめは風味も食感もとても良いです。また、たけのこも水煮にして真空パックや缶詰で一年中食べられますが、採れたてのたけのこは、より歯ごたえがシャキシャキとしています。わかめもたけのこもあまり好んで食べないという生徒もいますが、今日は素材の味がわかるようにシンプルな料理で提供しました。
今日はたけのこがメインなのでたくさん使っています。食感が残るように煮る時間は短めです。
わかめは出来上がりの直前に入れてさっと火を通します。
5月9日 ソフトフランスパン・シェパーズパイ・コロネーションサラダ・スコッチブロス・牛乳
今日はイギリス料理です。「シェパーズパイ」は家庭料理で、イギリスが舞台の物語「ハリー・ポッター」の中にも出てきます。シェパードは羊飼いのことを指す言葉であり、羊の肉で作ったミートソースの上にパイの皮に見立てたマッシュポテトをのせてオーブンで焼いて作る、ミートパイのようなものです。給食では、豚肉で代用して作りました。「コロネーションサラダ」のコロネーションとは、国王が即位のしるしとして王冠を頭にのせる「戴冠」を意味する言葉で、女王エリザベス2世が即位したときの戴冠式の晩餐会の際に考案された伝統的な料理です。「スコッチブロス」は、肉や野菜、麦などが入った、イギリスのスコットランドの代表的なスープです。今日は、シェパーズパイが人気だったようで、ボリュームがありましたが残菜はほとんどありませんでした。
シェパーズパイのミートソースは朝早くからよく煮込みました。
じゃが芋を蒸してつぶし、塩、こしょう、マーガリン、牛乳を加えて滑らかなマッシュポテトにします。
カップにミートソースを入れ、形を整えたマッシュポテトをかぶせます。
コロネーションサラダのドレッシングは、マヨネーズにカレー粉や白ワインなどを合わせたオリジナルの配合です。
蒸した鶏肉と野菜、ドレッシングを合わせます。カレーの風味が食欲をそそります。
スコッチブロスには押麦を入れました。食感もぷちぷちとしていて楽しいです。
5月7日 こぎつねご飯・ししゃもの磯辺揚げ・おひたし・新玉ねぎのみそ汁・牛乳
今日のみそ汁に入っている玉ねぎは、新玉ねぎです。普通の玉ねぎは収穫後、表皮を乾燥させて保存性を高めてから出荷されていますが、春先に採れる新玉ねぎは葉がみずみずしいうちに収穫し、すぐに出荷されます。新玉ねぎは柔らかくて、独特の辛味やにおいが少ないので、サラダなど生で食べるのもおすすめです。今日はみそ汁に入れましたが、甘みがあっておいしかったです。
5月2日 中華ちまき・レタスの中華おひたし・ワンタンスープ・冷凍みかん・牛乳
今日は、少し早いですが5月5日の「端午の節句」に合わせたメニューです。端午の節句は男の子の誕生や成長を祝う行事で、元気に成長し、立派な大人になってほしいという願いをこめてこいのぼりを飾ったり、縁起の良い柏もちやちまきを食べたりします。ちまきは日本の中でも地方によって違いますが、給食ではもち米に焼豚やにんじんなどの具材を混ぜて作ったおこわを一つ一つ竹の皮で包んだ中華ちまきを作りました。
こんなに大きな竹の皮で包んでいます。
焼豚、にんじん、干ししいたけ、しょうがを炒めます。
だし汁、調味料、浸水させたもち米を入れて強火で混ぜ続けます。
もち米が8割ほどの炊き具合になったら、竹の皮で包んで蒸します。
蒸し上がりました。竹の皮の良い香りがします。
中身はこのような感じになりました。もち米100%なのですごくもちもちです。
5月1日 肉汁うどん・海藻の和え物・抹茶ケーキ・牛乳
今日は、立春から数えて88日目にあたる「八十八夜」という日で、春から夏に変わる節目の日であり、田植えや茶摘みなど初夏の農作業を始める目安になっています。お茶は木の生命力が強く、葉を摘んでもまた新たに芽が出てくるので一年に3回ほど収穫されますが、中でもその年の最初の若い芽で作るお茶が新茶です。新茶には若々しい香りと新鮮な味わいがあり、旨味成分が多く含まれます。また、この日に摘んだお茶を飲むと、1年間健康でいられる、長生きできると伝えられています。給食では、八十八夜に合わせて抹茶ケーキを作りました。食べるとふわっと抹茶の香りが感じられるおいしいケーキでした。
抹茶の緑色がきれいです。
甘納豆も入れています。
甘納豆が全部にいきわたるように気を付けながらカップに生地を流し入れます。
粗熱を取ってから粉糖をふりかけると見た目もきれいです。