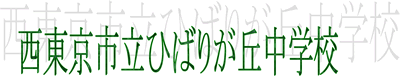1月の給食
更新日:2025年1月29日
毎日の給食
1月31日 ご飯・さばのねぎ塩焼き・梅おかか和え・芋団子汁・牛乳
じゃが芋には炭水化物だけでなくビタミンCも多く含まれています。ビタミンCは加熱すると壊れやすい性質がありますが、じゃが芋のビタミンCはでん粉質に守られているので、調理をしても壊れにくいという特徴があります。保存性の高い食品なので1年を通して色々な料理に使われますが、なかでもゆでたり蒸したりした芋をつぶしてでん粉と混ぜた芋団子や芋もちは、そのまま焼いたり、野菜などと一緒に汁に入れて北海道などで昔から食べられています。「すごくおいしかったです」と声をかけてくれた生徒もいて嬉しかったです。
蒸したじゃが芋をつぶして片栗粉、塩、砂糖を入れてこねます。
直径1.5cm程度の大きさに丸めます。
さっと下ゆでして汁に合わせます。
汁に入れて少し煮込むと、もちもちでとろっとなめらかな食感になりました。
1月30日 四川豆腐丼・中華風コーンスープ・はるみ・牛乳
今日の果物は、市場の出荷状況の影響により、甘平(かんぺい)からはるみに変わりました。はるみは、清見タンゴールとぽんかんをかけ合わせてできたかんきつです。実はデコポンも品種は違いますが同じかけ合わせでできているのではるみとデコポンは兄弟にあたります。みかんのように手でむけて、薄皮がとても薄いのでそのまま食べることができます。果肉はプチプチとはじけるような食感で、甘くて爽やかな果汁がたっぷりです。今日は小さめでしたがおいしかったです。
デコポンと兄弟というだけあって、デコポンほどではないですが「デコ」があるものも。
1月29日 キムタクご飯・山賊焼き・浅漬け・ひんのべ汁・牛乳
今日は、1年生が明日からスキー移動教室で行く菅平のある長野県の料理です。「キムタクご飯って何?」という声が多数聞こえてきましたが、キムチとたくあんの混ぜご飯で、長野県塩尻市の学校給食が発祥の料理です。昔から長野県はたくあんなどの漬物をよく食べていましたが、漬物があまり好きでない子供たちにもおいしく食べてもらいたいという思いから作られました。山賊焼きは鶏のから揚げのような料理ですが、山賊が物を「とりあげる」ことから、「鶏を揚げる」料理を山賊焼きと呼ぶようになりました。揚げ物料理なのに「焼き」という名前になっているのは、昔は油が貴重で少量の油で焼いていたためだそうです。ひんのべ汁は、季節の野菜やお肉などが入った汁物で、長野の代表的なみそである信州みそで味付けしました。小麦粉を練って作った生地を、ひっぱってのばして汁に入れることからこの名前が付けられました。
辛みのあるキムチとほんのり甘みのあるたくあんは意外と相性が良いようです。
山賊焼きは衣に米粉を使ってサクサクになるようにしてみました。
小麦粉を練って作った生地をひっぱってのばして汁に入れます。少し寝かせていたのでよくのびます。
小麦粉の生地が少し汁に溶け出てとろみがつきました。寒い日にぴったりな体の温まる汁です。
1月28日 手作り紫芋米粉パン・ペンネソテー・カレービーンズ・牛乳
今日のパンは、給食室で手作りした米粉パンです。米粉パンは昨年度から何度か作っていますが、紫芋パウダーを練り込んだパンは初めて作りました。焼き上がると焼き芋のような良い香りがして、中は鮮やかな紫色に仕上がりました。このパンは今日初めて給食で作ったことを伝えると、「もちもちでおいしいです」と言ってもらえたのでよかったです。
生地は約100個分ずつ4回に分けて練ります。
1個ずつきれいに丸めます。
ほんのり焼き色が付くように焼きました。
割ってみると中は鮮やかな紫色できれいです。
1月27日 梅ひじき菜飯・揚げじゃが芋のそぼろ煮・豆腐とねぎのみそ汁・いよかん・牛乳
今日の果物は、市場の出荷状況の影響により、はれひめからいよかんに変わりました。みかんやオレンジなどの柑橘類と呼ばれる果物は、インドや東南アジアで生まれたといわれ、世界中に100種類以上もあります。いよかんは山口県で誕生した日本独自の品種です。人工的に交配されて作られたわけではなく、みかん類とオレンジ類が自然交配したものと考えられていて、どのような組み合わせなのかその誕生はわかっていないそうです。今は品種改良されたおいしい柑橘類がたくさんありますが、昔からあるいよかんも甘くてジューシーでおいしいです。
色も形もきれいです。切る前からとても良い香りがしています。
1月24日 ハヤシライス・春雨サラダ・りんご・牛乳
今日は、タイムスリップ給食の最終日です。昭和40年代の後半になると、今までパンや麺類だけだった主食にご飯が復活しました。正式に導入されたのは、昭和51年のことです。当初はご飯を炊くための設備が整わず、おかずを作る鍋でご飯を炊く施設が多かったです。ご飯の導入により、メニューもよりいっそう豊かになり、今の給食のような形になっていきました。今日で学校給食週間は終わりですが、この機会に給食について家族で話してみたり、調べてみたりするといいですね。
1月23日 ソフト麺ミートソース・甘酢和え・黄桃・牛乳
今日は、タイムスリップ給食の4日目です。昭和30年代後半には脱脂粉乳のミルクが牛乳へと切り替わり、コッペパン以外のパンも出るようになりました。また、昭和38年には、ずっとパンばかりの給食に「ソフト麺」が登場しました。ソフト麺は、正式名称を「ソフトスパゲッティ式麺」と言い、学校給食向けに開発された日本特有の麺です。昭和40年頃から給食でよく使われるようになりました。スパゲッティとうどんの間のような麺で、スパゲッティのようにミートソースに絡めたり、うどんのようにカレーあんかけにつけて食べられていました。今では珍しく、ほとんど食べる機会のないソフト麺ですが、生徒には大人気でした。小中学生の頃、実際にソフト麺を食べていた先生から、当時の食べ方や思い出など貴重なお話しを聞くこともできました。
ソフト麺は袋ごと給食室で温めます。スパゲティとうどんのちょうど間くらいの太さの麺です。
給食のミートソースには、実はピーマンが入っています。知っている生徒はどのくらいいるでしょうか?
1月22日 コッペパン・いちごジャム・くじらの竜田揚げ・せん切りキャベツ・カレーシチュー・牛乳
今日は、タイムスリップ給食の3日目です。昭和16年に太平洋戦争が始まると、食料不足の影響で給食が中止されましたが、昭和20年に戦争が終わり、アメリカの民間団体からの支援物資やユニセフから寄付を受け、昭和21年に再開されました。この時は主食はなく、牛乳も貴重だったため脱脂粉乳が出されました。昭和25年には、アメリカから小麦粉が送られ、パン、おかず、ミルクの完全給食が始まりました。今日はその頃のメニューです。パンは大きなコッペパンで、ジャムやマーガリンが時々つきました。くじらは、当時高級品だったお肉の代わりに使われ、竜田揚げなどで出されていました。給食は主食がパンで、カレーライスにできなかったことから、パンに合うようにカレーシチューも作られていました。くじらが特に大人気で、キャベツと一緒にパンにはさんで食べるというおいしそうな食べ方をしている生徒もいました。
くじらは酒、しょうゆ、みりん、しょうがでしっかりと下味をします。
硬くならないように気を付けながらカラッと揚げます。
カレーシチューはシチューにカレー粉を入れてカレー風味にします。
ほんのり黄色いシチューができました。
1月21日 五色ご飯・さつま芋とちくわの天ぷら・こんにゃくの和え物・栄養みそ汁・牛乳
今日は、タイムスリップ給食の2日目です。昨日は日本で最初に出された明治22年の給食でしたが、今日は時代が進んで大正12年の給食です。大正12年の9月1日に関東大震災が発生し、栄養失調の子供が増えました。そこで国は、子供たちの栄養を改善するために給食を出すよう命令し、給食は全国で提供されるようになっていきました。この時のメニューが、「五色ご飯と栄養みそ汁」でした。五色ご飯は、鶏ひき肉、里芋、野菜が入ったご飯で、栄養みそ汁にもたくさんの野菜が入っていました。大正時代の給食メニューも好評でした。
里芋は蒸しておいて、ご飯に混ぜ込む具材が出来上がったところに合わせるときれいに仕上がります。
里芋が崩れないように気を付けながらご飯とよく混ぜ合わせます。
1月20日 おにぎり・鮭の塩焼き・青菜の漬物・芋煮汁・牛乳
1月24日から1月30日は、全国学校給食週間です。今年度は1.2年生の学校行事と重なる日が多いので、今週1週間で実施することにしました。「タイムスリップ給食」をテーマに、昔の給食の代表的なメニューを作ります。日本の学校給食は、明治22年に山形県鶴岡町の私立忠愛小学校で、お弁当を持って来られない子供のために食事を提供したのが始まりとされています。この時の献立が、今日の給食と同じ「おにぎり、塩鮭、漬物」でした。今日は、栄養バランスなどを考え、山形県の郷土料理の芋煮をアレンジした汁物と牛乳もつけましたが、食べ物があまりなかったこの時代には、おにぎりと少しのおかずだけでもごちそうでした。昔は汁物も牛乳もなかったことを伝えると、寂しいなと言っている生徒もいました。今日のおにぎりはとても好評で、ほとんど残食がありませんでした。明日は、関東大震災後の大正12年頃の給食をモデルにした献立です。
1個ずつ計量しながらにぎり、アルミホイルで包みました。約1200個です。ホイルで包んでいるので乾燥せず、食べるときも温かいです。
大きな釜で煮ている様子は、まさに山形の芋煮会のようです。
1月17日 ドリア・コーンフレークサラダ・ベーコンポテトスープ・牛乳
今からちょうど30年前の1月17日、阪神・淡路大震災が発生しました。冬の寒い時期に被災した人たちにとって、電気もガスも止まってしまった状況では、温かい食事はとても貴重なものでした。昔は非常食というと乾パンが主流でしたが、この震災以降、お湯があれば温かいご飯が食べられる「アルファ化米」の良さが認められるようになりました。西東京市でも、災害時の非常用食糧としてアルファ化米を備蓄していて、賞味期限切れにならないように定期的に新しいものに入れ替えています。この入れ替えたアルファ化米を使って、今日のドリアを作りました。災害時には食べ慣れないものを食べることも多くなるので、時々普段の食事にも取り入れて、慣れておくことも大切ですね。
アルファ化米はお湯を入れるだけで炊けます。今日はターメリックも一緒に入れました。
今日のホワイトソースは豆乳で作りました。コクを出すためにみそを入れています。
カップに黄色く炊きあがったアルファ化米を入れ、ホワイトソースをかけます。
チーズとパン粉、パセリをかけて、オーブンで焼きます。
チーズがとろけ、焼き色がついておいしそうにできました。
1月16日 ご飯・ムロメンチ・小松菜ののり和え・ちゃんこ汁・東京牛乳
今日は、2年生が24日に校外学習で行く都内巡りに合わせ、東京都にまつわる食材や料理を取り入れました。「ムロメンチ」は、三宅島でとれたムロアジを使ったメンチカツです。ムロアジは東京の海域では伊豆諸島から小笠原諸島まで広く分布する魚です。小松菜は江戸時代に現在の江戸川区周辺の小松川で栽培されていたことから名付けられた野菜で、西東京市でも多く作られています。「ちゃんこ汁」のちゃんこというのは力士の食事をさす言葉で、相撲部屋がある両国から広まった料理です。力士たちの体を作るために、肉や魚、野菜などをたっぷりと使ったボリューム満点で栄養価の高い料理になっています。
三宅島でとれたムロアジのミンチです。臭み消しにしょうがやにんにくも入れます。
小判型にして、衣をつけて揚げます。
カラッと良い色に揚がりました。
ちゃんこ汁は野菜がたっぷり。あっさりとした中に食材の旨味が詰まっています。
1月15日 五目旨煮丼・わかめとじゃこの和え物・お汁粉・牛乳
日本では、昔から1月15日を「小正月」と呼んでいます。正月のイベントの一つでもあり、新年から続いた様々な正月行事の締めくくりにあたるものが小正月です。小正月には、正月飾りや神社のお札・お守りなどの縁起物を片付けるために「どんど焼き」が行われます。役目を終えた道具を焼き、お焚き上げを行うのが目的です。この時に焚き上げられた煙とともに、お正月に来てくれて年神様が天に帰っていき、正月行事を終えると考えられています。また、この日には一年の健康と厄除けを願って「小豆粥」を食べることが多いです。赤いものには邪気を払う力があるとされ、小豆にも同じ力が宿っているとされています。今日の給食では小豆をよく煮て、手作りの白玉団子を入れたお汁粉を作りました。
小豆は数回ゆでこぼしてから柔らかくなるまで煮ていきます。
白玉団子は一人3個になるように作ります。今日は大きめです。
ゆでるとさらに大きくなりました。数をかぞえて先に食缶に配食しておきます。
汁を注いで白玉団子と軽く混ぜ合わせます。
1月14日 ガーリックライス・フェジョアーダ・パステウ・ヴィナグレッチサラダ・コーヒー牛乳
今日は、ブラジルの料理です。ブラジルには様々な人種が暮らしているので食品も多様なものが使われていますが、特に豆や米が多く使われています。「フェジョアーダ」はその代表的な料理で、豆と豚肉、ソーセージを煮込んだものをご飯にかけて食べる、ブラジルの国民食とも言われる料理です。「パステウ」は、小麦粉でできた薄い生地に、チーズや肉を包んで揚げたもので、市場の屋台やサッカースタジアムなどで売られているファストフードです。「ヴィナグレッチサラダ」は、酢にトマトや玉ねぎなどの野菜を混ぜたドレッシングで味付けしたサラダです。また、ブラジルはコーヒー豆の生産量が世界一なので、今日の飲み物はコーヒー牛乳にしました。日本の料理とは雰囲気が違うので苦手という生徒もいたかもしれませんが、少しだけブラジルの雰囲気を味わうことができたのではないかと思います。
今日の豆は白いんげん豆と金時豆です。柔らかく煮てから合わせます。
豚肉やソーセージ、野菜がゴロゴロとたくさん入っています。
炒めて味付けしたひき肉、チーズ、じゃが芋などの具材をぎょうざの皮で包みます。
油で揚げる皮はパリッと、中の具材はトロっとした仕上がりになりました。
季節的に生のトマトを使うのは難しいのでトマト缶を入れたドレッシングにしました。見た目は辛そうに見えますが、酸味が効いたさっぱりとした味です。
1月10日 七草うどん・昆布和え・チーズ磯辺もち・牛乳
少し前になりますが、1月7日は「人日(じんじつ)の節句」でした。春の七草を入れた七草がゆを食べて邪気を払い無病息災を願う日なので、それに合わせて今日の給食は春の七草のうちの「せり、すずな(かぶ)、すずしろ(大根)」を入れたうどんにしました。また、明日11日は「鏡開き」で、お正月にお供えしていた鏡もちをいただく日です。鏡もちには年神様の魂が宿っているので、食べることで年神様の力をわけていただき、1年間の無病息災を願います。鏡もちは、木づちなどで割っていただきますが、「割る」や「切る」という言葉は縁起が悪いとされ、「開く」という言葉を使うようになりました。今回は、おもちにしょうゆをからめ、チーズをのせてのりを巻いて焼いた「チーズ磯辺もち」です。アルミホイルで包んで焼いているので、保温されて柔らかい状態で食べることができました。
せりとすずな(かぶ)はすぐに煮えるので出来上がりの直前に加えます。
具だくさんで栄養満点。お正月のごちそうで疲れた胃腸も元気になりそうです。
しょうゆをからめたもちにチーズをのせて、のりを巻いてアルミホイルでぴったりと包みます。
オーブンで焼くとこのような仕上がりになりました。
1月9日 豆じゃこチャーハン・野菜チップス・生揚げとチンゲン菜のスープ・牛乳
今日の野菜チップスは、じゃが芋、さつま芋、れんこんの3種類の食材を使っています。パリッと軽い仕上がりになるように、今日は厚さ1mmくらいにとても薄くスライスしました。水にさらしてアクを抜いてから水分をしっかり切って油でじっくり揚げるとパリパリの野菜チップスが出来上がりました。素材の味がわかるように塩は控えめにしました。チップスはやはり生徒に人気で、ほとんどのクラスが完食でした。
れんこんは一枚一枚包丁で薄く切っています。とても大変ですが、機械よりもきれいに仕上がります。
低温の油でじっくりと揚げます。
素材の味が活きるように、塩は控えめにまぶします。
1月8日 ポークカレーライス・グリーンサラダ・キャロットゼリー・牛乳
新しい年を迎え、3学期の給食も始まりました。3学期もよろしくお願いいたします。今日のゼリーはにんじんをすりおろして入れたキャロットゼリーです。蒸して柔らかくしたにんじんをみかんジュースと一緒にミキサーにかけているので、にんじんが苦手な人でも食べやすい味になっています。素材を活かしたほど良い甘さで、カレーの後に食べるとさっぱりしておいしかったです。
にんじんが入っているので、みかんジュースだけで作ったみかんゼリーよりも濃いオレンジ色がきれいです。