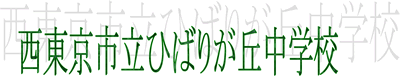6月の給食
更新日:2024年9月30日
毎日の給食
6月28日 五目旨煮丼・キャベツとじゃこの和え物・水無月・牛乳
あ明治時代の初めまで使われていた旧暦では、6月を別名で「水無月」と呼んでいました。その名残で、今でも6月のことを「水無月」と呼ぶことがあります。この「水無月」の名前がついた和菓子が今日のデザートです。一年の折り返しにあたる6月30日に、京都の神社では「夏越の祓」という儀式が行われています。夏越の祓は、半年の間に身に溜まった穢れを落とし、残りの半年の無病息災を願って行われます。神社には「茅の輪」という人の背丈よりも大きな輪を設けられ、参拝者はここをくぐって厄除けをします。そして、この時にお供えされるのが水無月です。小麦粉と上新粉で作ったういろうの生地を柔らかめに蒸し、上に小豆を散らしてまた蒸して作られます。小豆には魔除けの意味があり、三角の形は暑さをしのぐ氷を表している、とても縁起の良いお菓子です。残り半年、病気をせずに元気に過ごせるように願いながらいただきました。
小麦粉、上新粉、砂糖に水を入れて生地を作ります。
生地の4/5を天板に分けて流し入れます。
一度蒸します。
1/5残しておいた生地に水を入れてさらっした生地にして、甘納豆と混ぜて、蒸した生地の上に流し入れます。
もう一度蒸したらこのような仕上がりになりました。
三角形に切り分けたら完成です。
6月27日 パエリア・エンパナーダ・ソパデアホ・牛乳
今日は、スペインの料理です。ヨーロッパ南西部のイベリア半島に位置するスペインは、年間を通して晴れの日が多く、じめじめすることがない気候で、とても過ごしやすい国です。地中海沿岸のスペインでは稲作も行われていて、海や山の幸をたっぷり使ったお米料理の「パエリア」が有名です。「エンパナーダ」は、肉や野菜などの具を中に詰めたパンやパイのような料理です。給食では、ぎょうざの皮で包んで作りました。「ソパ・デ・アホ」のソパはスープ、アホはにんにくを意味するスペイン語です。硬くなってしまったパンをおいしく食べるために考えられました。食缶の蓋を開けると同時に、色々なクラスから「いい香り〜」という声が聞こえてきました。今日はエンパナーダが人気でした。
パエリアは、いか、えび、たらなど魚介たっぷりです。
高級なサフランの代わりにターメリックで炊いた黄色いご飯に具材を混ぜ合わせます。
エンパナーダの中身は豚ひき肉、大豆、じゃが芋、ピーマンにしました。クミンやパプリカなどの香辛料で味付けしています。
ぎょうざの皮で包み、フォークの背で閉じながら模様を付けます。
全部がきれいに色づくように油を回しかけながら揚げていきます。
ソパ・デ・アホにはにんにくがたっぷり入ります。
にんにくが利いたトマトとふんわり卵のスープができました。
硬いパンの代わりに、食パンを小さく切ってオーブンで1時間以上じっくりと焼いてクルトンを作りました。サクサク感を保つために、クルトンは教室で配膳の時にスープを盛り付けてから上に乗せました。
6月21日 たこ飯・生揚げのひき肉あんかけ・ゆかり和え・冬瓜汁・牛乳
今日は、一年で一番昼の時間が長いと言われる「夏至」の日です。夏至の時期に食べられているものは日本各地でいろいろありますが、今日はその中から関西でよく食べられている「たこ」を具材に混ぜ込んだ「たこ飯」と、一般的に食べられることの多い「冬瓜」をたくさん使った「冬瓜汁」を作りました。どちらかと言えば大人が好きそうなメニューでしたが、たこ飯はおかわりをしている生徒もたくさんいて、残食が少なかったです。
たこは硬くならないように気を付けながら、他の具材と一緒に炒め煮にします。
少ししょうゆと酒を入れて炊いたご飯と混ぜ合わせたら完成です。
冬瓜は少し厚めのいちょう切りにします。
冬瓜はすぐ煮えてしまうので、食べる頃にちょうどよい硬さになるように考えて作ります。
6月20日 ポークカレーライス・ハニーサラダ・すいか・牛乳
すいかは漢字で「西の瓜」と書きます。生まれはアフリカですが、中国では「西から伝えられた瓜」としてこの漢字が当てられ、それが日本に伝わりました。英語では「watermelon(ウォーターメロン)」と言いますが、その名のとおり約90%が水分でできているので、体を素早く冷やし、熱中症予防にも役立ちます。あまいですが、以外にもカロリーは低い食べ物です。今日のすいかは、群馬県産の藪塚こだま西瓜でした。藪塚地区は全国でも日照量が多く、水はけのよい土壌に恵まれていることでおいしいすいかが生産できるそうです。とてもあまくておいしいすいかでした。
小玉すいかですがバレーボールくらい大きいです。
人数分に切り分けても立派なサイズで満足感があります。
6月19日 ご飯・魚の香味揚げ・ほうれん草ののり和え・具たっぷり豚汁・牛乳
6月19日は「食育の日」です。平成17年に「食育基本法」という法律が制定され、6月は「食育月間」、毎月19日は「食育の日」となっています。今日は、「栄養バランスのとれた食事」と「減塩」をテーマにした献立にしました。今日の給食は、主食・主菜・副菜がそろった献立で、一人分全て食べると120gの野菜が摂取できるようになっています。また、汁物を具だくさんにして汁を減らしたり、出汁でうま味を利かせて塩分の少ないみそで味付けしたりなど、減塩するための工夫をして作りました。野菜たっぷり、減塩となると生徒はあまり好まないかと少し心配しましたが、しっかり食べていました。
今日の魚はモウカサメです。香味野菜を使うのも減塩におすすめの方法の一つです。
和え物にはこの大量のほうれん草を使っています。ゆでるとかさが減るのでたくさん食べられます。
昆布とかつおぶしでおいしい出汁を取っています。
豚汁はこんなに具だくさんです。
6月18日 ビスキュイパン・ポテトサラダ・ABCスープ・牛乳
ビスキュイパンの「ビスキュイ」とは、フランス語で「二度焼く」という意味ですが、実際には小麦粉にバターや卵、牛乳などを加えて焼いた、フランスの焼き菓子の総称になっています。「ビスケット」の語源にもなった言葉です。ビスキュイパンは、小麦粉や卵、砂糖などを混ぜて作ったあまい生地をパンにのせて焼いた、メロンパンのようなパンです。焼くことによって上にのせた生地がビスケットのように香ばしく、サクサクとした食感になります。
クッキー生地をよく混ぜ合わせます。給食では牛乳の代わりに豆乳を使っています。
丸パンにクッキー生地を塗りつけます。
グラニュー糖をかけて、オーブンで焼きます。
表面がサクサクに焼きあがりました。とても良い香りが漂っていました。
6月17日 まぜまぜビビンバ・チャプチェ・トックスープ・さくらんぼ・牛乳
さくらんぼのなる木とお花見の時に見る桜の木は同じ桜ではありますが、まったく別の種類の木です。観賞用の桜の木の実はとても小さく、酸味や苦味があって食べるのには適しません。さくらんぼの産地として有名な山形県は、強風が吹きにくく、夏は暑くて梅雨のときも雨が少ないなど、さくらんぼが育つのに適した気候であり、国内生産の約7割を占めています。今日のさくらんぼは山形県産の「やまがた紅王」という、令和5年に本格的に販売が開始された新品種です。国内最大級の大玉で、その大きさと鮮やかな紅色が王様の風格を表していることから命名されたそうです。大きくてとてもあまくておいしいさくらんぼでした。
しっかりときれいな紅色に色づいています。見た目だけでなく味も抜群です。
6月14日 豚肉の時雨ご飯・揚げ出し豆腐・野菜の昆布和え・大根とわかめのみそ汁・牛乳
今日のご飯は、豚肉のしぐれ煮を混ぜたご飯です。しぐれ煮とは、しょうがを使ったつくだ煮のことです。さっと煮つけたところや、色々な風味が口の中を通り過ぎることから、ぱらぱらと通り雨のように降る雨の「時雨(しぐれ)」にたとえて「しぐれ煮」と名付けられたと言われています。ハマグリなどの具や牛肉で作られることが多いですが、給食では豚肉を使って作りました。甘辛い味が生徒にも人気だったようです。
じっくり煮含めて時雨煮を作ってご飯に混ぜました。
揚げ出し豆腐は、小麦粉とコーンスターチを豆腐にまぶして揚げています。
6月13日 ツナと大根のスパゲティ・コーンサラダ・レモンケーキ・牛乳
大根の品種は100種類以上あると言われています。育てる土の状態などによって形が変わりやすい野菜なので、すらっと長い東京の「練馬大根」、大きくて中央がふくらんでいる神奈川の「三浦大根」、かぶのような形をした京都の「聖護院大根」、世界一大きくて重い鹿児島の「桜島大根」など、地域によって形はさまざまです。色も白だけでなく、黒や赤もあります。大根には色々な酵素が含まれていて、炭水化物やたんぱく質、脂質の消化を助ける働きがあり、胃もたれや胸やけの予防・改善にも役立ちます。今日の給食は、大根をすりおろしてスパゲティのソースにしました。大根おろしをかけるとさっぱりと食べられます。
今日は地元の農家さんから69kgもの大根を届けていただきました。
大根の辛味や苦味を和らげるために、まずはすりおろした大根だけで加熱します。
調味料を加えて少し煮詰めたら大根おろしソースの完成です。
6月12日 大山おこわ・ししゃものカレー風味焼き・らっきょうのごま和え・じゃぶ汁・牛乳
鳥取県は、緑豊かな山と海があり、四季おりおりの自然が楽しめる豊かなところです。鳥取県の西側には、中国地方最高峰の「大山」という山があります。「大山おこわ」は、その山のふもとでお祭りや季節の行事などの時に昔から食べられてきた家庭料理です。もともとは大山で修業する人たちにふるまわれてい来た大山寺のおこわが家庭にも広がり、大山おこわになったそうです。「らっきょう」は、鳥取県の特産品です。鳥取県には鳥取砂丘という有名な砂丘がありますが、砂丘などの水はけがよくて栄養分の少ない土地でもらっきょうは育つという特性があります。「じゃぶ汁」は、野菜やきのこ、豆腐、肉などを入れてごった煮にした料理です。豆腐や野菜をじゃぶじゃぶ煮ることや、煮込んでいるうちにじゃぶじゃぶと水分が出てくることから名付けられました。今日は、大山のふもとで育てられた「大山どり」という鳥取県の銘柄鶏を、大山おこわとじゃぶ汁に使いました。
今日は大山どりを使っています。おこわに使う方は下味をつけてから炒めました。
ごぼうやにんじん、椎茸、油揚げと一緒に炒め煮にして味を煮含めていきます。
もち米を入れて炊いたご飯と具材をよく混ぜ合わせたら完成です。
らっきょうは甘酢漬けになっているものを使いました。
苦手な人でも食べやすいように薄くスライスして入れました。
今日はごまをたっぷり入れた手作りのドレッシングで和えました。
お肉や野菜、豆腐などが入った具だくさんの汁物です。少し砂糖も入って甘めの仕上がりです。
6月11日 ハヤシライス・チリビーンズサラダ・メロン・牛乳
今日のメロンは、茨城県産の「ユウカメロン」です。ユウカメロンは栽培が難しく、量産できないため市場にはなかなか出回らない希少品種です。香りがとても良いことから「優香(ゆうか)」と命名されました。熟すと表面の皮が緑色から黄色に変わり始め、収穫する時期を色で知らせてくれるユニークなメロンです。種の部分が少なく、皮も薄いため果肉がとても厚く、肉質は柔らかいです。今日のメロンはちょうど食べ頃で、とても良い香りで甘くてジューシーでおいしかったです。
とても大きなメロンが届きました。皮もちゃんと黄色くなっていて食べ頃です。
きれいに種を取ってカットします。少し離れたところにいても良い香りが届きました。
6月10日 いわしのひつまぶし風ご飯・梅おかか和え・すまし汁・あじさいゼリー・牛乳
今日は、暦の上で梅雨が始まるとされている「入梅」の日です。梅雨は、字のごとく梅が収穫される季節です。日本には古くからこの時期にしか手に入らない梅を使って、梅干しを作る習慣があります。新鮮な梅を塩で1か月ほど漬け込み、梅雨が明けて晴れが続きそうな日に3日間くらい天日干しすると、梅干しが出来上がります。梅の実は生では食べられませんが、梅干しにすることで10年以上も保存することができるようになります。今日の和え物は、梅を入れて作ったドレッシングで味付けしました。いわしは「入梅いわし」という言葉があるほど入梅の時期の代表的な魚で、一年で最も脂がのっていておいしいとされています。今日のご飯はいわしを名古屋名物の「ひつまぶし」風にしています。お茶や出汁をかけて食べたりもするので、今日のすまし汁も、かけて食べてもおいしいように作りました。また、デザートは梅雨の時期に花を咲かせる「あじさい」に見立てた手作りのあじさいゼリーです。ぶどうジュースとアセロラジュースで作った2色のゼリーを細かく刻んでカップに入れ、透明なゼリー液を上からかけて雨に濡れる2色のあじさいをイメージしました。魚があまり好きでない生徒が多いのでひつまぶし風のご飯にしてみましたが、思ったよりもおかわりしている生徒も多かったです。
いわしは魚屋さんに短冊切りにしてもらいました。しょうが、酒、しょうゆで軽く下味をつけます。
油でカラッと揚げます。
手作りのタレを絡めると、うなぎのかば焼きのようにできました。
ごはんを盛り付けた上にびっしりといわしのかば焼きをのせ、ねぎを散らしたら完成です。
すまし汁に入れると本当のひつまぶしのようです。かば焼きのしっかりした味が出汁の味で中和されて食べやすいです。
濃い紫色のぶどうゼリー液を薄く流して冷やし固め、1cmのさいの目切りにします。
薄いピンク色のアセロラゼリーも同じように作ります。
カップに2種類のゼリーを入れます。
上から透明なゼリー液を注ぎ入れて固めます。
あじさいゼリーの完成です。
6月7日 ごま塩ご飯・野菜の肉巻き・カミカミ和え・切干大根のみそ汁・牛乳
6月4日から10日は、「歯と口の健康週間」です。よくかんで食べると、肥満予防や味覚の発達、脳の発達、歯の病気の予防など、良い効果がたくさんあります。現代の食事はかみごたえのあまりない柔らかい食品が多いため、昭和初期の食事と比べてかむ回数が半分以下になっています。健康な歯と口を保つために、かみごたえのある食べ物を意識して食べたり、食後に必ず歯をみがいたりして、歯を大切にするために自分でできることを実践していきたいですね。今日の給食は、焼いた豚肉やするめいか、切干大根など、特にかみごたえのある食品をたくさん取り入れて、カミカミメニューにしました。
野菜に肉巻きは、豚肉でにんじんとさやいんげんを巻きました。
約1200個、きれいに巻けました。綴じ目を下にして、オーブンで焼きます。
甘辛いタレに浸して味をつけてから配缶します。
みそ汁には切干大根がたくさん入っています。シャキシャキ感がしっかり残ってかみごたえ抜群です。
6月6日 そら豆と卵のチャーハン・カリカリグリンピースポテト・豆腐とチンゲン菜のスープ・牛乳
そら豆は数々の古い遺跡から出てきていて、世界最古の農作物の一つと言われています。さやが上向きにつくので、「空を向いた豆」からそら豆と名付けられました。4月から6月の初夏が旬で、鮮度が落ちやすいのでおいしい期間は収穫から3日間とも言われます。グリンピースはさやえんどうが成長したもので、さらに成長するとえんどう豆になります。冷凍や缶詰などで一年中食べることができますが、生のものは今の時期にしか手に入らないので貴重です。今日は、IJ学級の生徒が全校分のそら豆476さやとグリンピース1846さやの中の豆を出す作業をしてくれました。丁寧かつ素早い作業のおかげで、おいしい給食を作ることができました。そら豆もグリンピースも苦手な生徒が多めですが、そんな生徒にもなんとか食べてもらいたいと思っていつもとは違う料理にしてみました。どちらの料理もたくさん食べてもらえて残食が少なかったので嬉しかったです。
立派なそら豆です。豆が4つ入っていそうな大きなものもあります。
グリンピースもしっかりとした大きさがあります。
そら豆は少し力がいりますが、丁寧にむいています。「中の白い綿毛がすごくふわふわ!」とみんな言っていました。
グリンピースはそら豆より簡単にむけていました。豆が転がらないように丁寧に作業しています。
「9個も入っていました!」と見せてくれました。
そら豆は塩ゆでしてから食べやすいように薄皮を丁寧にむきます。
チャーハンの具材と合わせると彩りもきれいです。
グリンピースは片栗粉をまぶして揚げます。
カリカリになるまで揚げます。
同じくカリカリに揚げたじゃが芋と合わせ、スパイスをまぶしたら完成です。
6月5日 ガーリックトースト・おかひじきのサラダ・豆乳コーンチャウダー・コーヒー牛乳
「おかひじき」は、もともと日当たりの良い海岸や砂丘などに自生する野草で、日本では古くから食べられてきました。見た目が海藻のひじきに似ているので「陸のひじき」と呼ばれ、おかひじきと名付けられました。現在は山形県の内陸を中心に、食用として栽培されています。シャキシャキとした食感で、野菜が苦手な人でも食べやすい、くせのない味です。カルシウムやカリウム、鉄、マグネシウム、ビタミンC、ビタミンAなどミネラル豊富で、ひじきと同じくらい栄養満点な食材です。今日はさっぱりとしたサラダにしました。
確かにおかひじきはひじきに似ている感じがします。
シャキシャキ感が残るようにゆでます。
6月4日 ご飯・鶏のから揚げレモンソース・からし和え・五目汁・牛乳
今日のから揚げには、レモンを入れたソースがかかっています。レモンはそのまま食べるととても酸っぱいですが、この酸味のもとはクエン酸です。クエン酸は疲労物質である乳酸を素早く分解して、疲労回復をうながすと言われています。また、さわやかな香りにリモネンという成分で、不安やストレスを和らげるリラクゼーション効果があるとされています。運動会の疲れが残っていないか心配していましたが、から揚げじゃんけんの声が元気に響き渡っていたので良かったです。
今日は生のレモンをしぼって使いました。良い香りです。
レモンの搾り汁を入れて作ったソースを、カラッと揚げたから揚げにかけます。