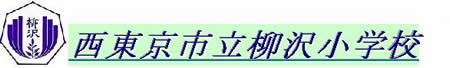学校長挨拶
更新日:2025年4月16日
令和7年度 学校長挨拶
西東京市立柳沢小学校 第12代校長 橋本 誠之
本校は、閑静な住宅街の中にある教育施設や緑地公園に隣接した西東京市の文教地区に位置する自然豊かな学校です。芝生の校庭、中庭の蛍池、シンボルツリーのメタセコイヤ並木、そして、校庭に鎮座するケヤキの巨木は圧巻です。通常学級以外に知的障害児学級と自閉症・情緒障害児学級が併設されており、スクールバスで通学する児童もおります。
今年度、本校は開校50周年の佳節を迎えました。それに伴い、わが校のマスコットキャラクターである「やぎんちゃん」が開校50周年Verにバージョンアップしました。また、開校50周年記念事業として、記念式典や児童集会などを計画しております。
コミュニティ・スクール2年目の本年、昨年度以上に、近隣の大学や高等学校をはじめ、西東京市の商工会やアスタ西東京、NPO法人、地元の農園、青少年育成会などの多くの団体と連携を深め、ふるさと探究学習をはじめとする学校教育の充実を推進してまいりました。また、今年度は西東京市以外の公立学校の群馬県水上市のみなかみ小学校との現地交流、台湾の公立小学校とのオンライン交流を深めてまいります。
昨年度は西東京市教育委員会学校教育研究奨励事業研究指定校の初年度として、児童一人一人の可能性を最大限に伸ばすことを目標に個別最適な学びの充実をめざし、校内では30回以上の研究授業の実践を積み重ねてまいりました。2年目の今年度は、個別最適な学びと諄動的な学びの一体的な充実をめざした授業改善を目標に取り組みます。2年間の集大成として、11月27日(木曜日)には研究発表会を実施し、西東京市内外に研究の成果を報告します。
最後に、校長として着任3年目を迎えます。地域や保護者の皆様をはじめ、学校を支えてくださる全ての方々に感謝の思いを伝えるとともに、次の10年へ向けての新たな出発を決意する50周年式典を10月23日に控えております。これからも本校を愛し、支えていただけますよう重ねてお願い申し上げます。
令和7年度 学校経営方針
教育理念 及び 教育目標
人間尊重の精神を基調とし、「確かな学力」「健やかな体」「豊かな心」を備え、他者と協働して、高い志をもち、新たな時代を切り拓く資質と能力をもつ児童を育成する。
◎ 考えて行動する子 〇思いやりのある子 ○ きたえる子
<目指す学校像>
教職員、保護者、地域が相互に連携して、かけがえのない子供一人一人の個性や能力を最大限に伸ばす学校を目指す。
○笑顔かがやく柳小の子(笑顔あふれる学校)
○みんなで育てる柳小の子(教職員が協働する学校)
○家庭・地域との「共育」を推進し、家庭・地域から信頼される学校
<目指す児童像>
○学ぶ意欲をもち、よく考えて課題を解決する子
○互いの良さを求め、協力して行動する子
○心身ともに健康で、目標に向かって粘り強く取り組む子
<目指す教師像> 【西東京あったか先生】
○「甘やかすことではない優しさ 怒鳴ることのない厳しさ」を持ち合わせた教師
〇 地域や保護者、同僚に常に感謝の心をもち、絶えず研究と修養に努める教師
○「子供を育てるプロ」として10箇条を意識した教師
(1) 子供の心を敏感に察知しよう。
(2) 子供を柔軟な見方で見よう。
(3) 子供に焦らず接しよう。
(4) 子供に期待をもって関わろう
(5) 子供に温かい関心をもとう。
(6) 子供とともに歩もう。
(7) 子供一人一人の身になって考えよう
(8) 子供のよいモデルになろう
(9) 子供に時として厳しく接しよう
(10) 子供の前で明るい大人であろう
経営理念 学校が果たす役割
目指す学校像1 笑顔かがやく柳小の子(笑顔あふれる学校)
(1)すべての児童が笑顔で登校し、自分の居場所があり、安心して学校生活が送れる学校
知・徳・体のバランスのとれた児童の育成を目指し教育活動を進めていく上で、その土台となる、すべての児 童の居場所(安心感・所属感)があり、和やかで活気に満ち、豊かなつながりを実感できる集団づくりを大切にしていきます。
集団の規律を保つことが、児童一人一人の安心感を生む。そのために教員は子供に判断基準である(柳沢小生活スタンダード、学習スタンダード、学校SNSルール等)を明確に示し、指導を積み重ねていくことを指導の基本とする。集団の規律を保つことが、未然防止につながり、児童が安心して落ち着いた学校生活を送ることができる。
(2)学びの主体者としての基礎を培う。(主体的・対話的な深い学びの実現を目指す)
小学校は、児童が生涯にわたり学習の主体者として、学び続ける基礎を培う時期である。児童に学習への構え、集団行動の規律を身に付けさせ、落ち着いた学校生活を送らせること、基礎的となる知識や技能、基本的な能力、思考力、判断力、表現力等を育み、主体的に学習する態度を養うことを目指す。学校は、「わかる喜び」「できる楽しさ」「使える実感」を味わえる授業を行うように努め、児童に確かな学力を付けることを目指す。児童が楽しい学校生活を送り、温かい人間関係の中で、関わり合い、学び合い、高め合う教育活動を行うことにより児童の学びを確立する。
目指す学校像2 みんなで育てる柳小の子(教職員が協働する学校をつくるために)
(1)校内における協働体制の構築
「情報の共有・意思疎通・共通実践」を徹底し、教育活動を推進する。学級担任は、自身の学級だけではなく学年全体の指導に当たる。交換授業や合同授業を意図的に計画し、複数の教員で児童を指導する。全教職員が全児童の指導に当たることを基本とし、教員間、職員間はもとより、教員・職員間においても「柳小の児童のために」を合い言葉に連携を図り、教育活動を推進する。
(2)自立した職務が学校としての組織力を高める。
職層および職務内容を把握し、職務を遂行するために集団の規律を遵守する。教師集団が子供に示した判断基準に従い、指導を積み重ねていくことで、児童一人一人に安心感を生む。いじめの未然防止につながり、児童が安心して落ち着いた学校生活を送ることができると考える。教師自身の笑顔や明るさが児童の心の安定につながることを忘れてはならない。
目指す学校像3 家庭・地域との「共有」を推進し、家庭・地域から信頼される学校をつくために
(1) 教育への信頼は、学校自らの手で獲得する。
公教育は、保護者や地域住民の信頼の上に成り立っている。教職員は、それぞれの専門職としての資質向上をめざし、悉皆研修、専門性向上に寄与する研修に進んで参加し、職層に応じた校内研修を受講し、力量を高めていく。また、教育公務員、都、市に勤務する公務員として、職務の厳正を図り、よりよい接遇に務める。柳沢小学校は、絶対に服務事故を起こさせない。出さない。見逃さない。
(2) 家庭、地域の期待や思いを受け止め、共にある学校を目指す。
学校評価の結果や日常における家庭や地域の学校への期待や思いを真摯に受け止め、児童の願い、保護者の願い、地域の願い、学校の願いを教育活動に反映させていく。そして、児童の健やかな成長を願い、地域、保護者と学校が密接な連携を図り、コミュニティ・スクールとして、地域のハブ的役割を果たしていく。
(3) 危機管理意識を常にもち、迅速な対応を務める。
「報告、連絡、相談」を徹底し教職員の連携を密にし、災害・事故等への適切な対応ができる校内体制および教育計画の再確認と常時改善を確立する。さらに、いじめ、事件・事故等の事案に対し、正確な事実の時系列を記録する。日頃から早期対応・早期解決・未然防止に務める。
中期経営目標
(1) 学校組織での対応
今後、人員の入替が活発になる時期になる。そのため、学校の組織力強化が急務となることが予想される。以下の方策を行う。
- 「一人で抱えない」を合い言葉に組織対応(教職員集団)で対応に当たる。
- 「学習のきまり」「生活のきまり」を基準とし、全校統一の指導を実施する。
- 計画的な人事異動を行い、教員間のバランスを向上させる。
(2)授業力の向上
学習指導要領が示す主体的・対話的で深い学びの実現を目指す。個別最適な学びと協働的な学びの一体化の 充実を目指し、個を意識した質の高い授業を目指すために以下の方策を実施する。
(1) 令和6年度、7年度西東京市教育委員会研究奨励校として、年間8回以上の研究授業に取り組み、組織的に授業 改善を図り、学校の教育力向上を図る。
(2) 日常の授業観察の充実を図る。(毎日、少しずつでも全学級の授業を見せていただく。)
(3) 互いの授業を見合い、学び合える環境づくりをする。(観察授業、校内研究)
(4) ON-JT研修、OFF-JT研修の充実を図る。
(3)健康の保持増進と体力向上
カリキュラムマネジメント視点に立ち、全教育活動を通して子供の体力向上と健康の保持増進を図る。令和5年度の新体力テストの結果から重点項目を分析し、改善に努める。
- どの子も運動する楽しさや喜びを味わえるための授業改善に努める
- 体育的活動を充実し、日常化を図る。(体育朝会、縄跳びやマラソン月間等)
- 学校のリーダーシップのもと家庭、地域と連携し、子供の体力向上と健康の保持増進に努める。(コミュニティ・スクール)
- 休み時間の外遊び励行し、教員も子供たちと共に過ごし、児童理解に努める。
(4)ICT教育の推進
(1) タブレット端末・ICT教育機器を活用した授業研究・指導技術の開発
(デジタル教科書、アプリケーションソフトの活用等)
(2) 児童が学習ツールとして、タブレット端末を活用するための基礎的技能・基本的能力の向上を図る。
- SNS学校ルール、SNS家庭ルールの見直し・更新を行い、児童のみならず保護者へのモラル向上を徹底する。
(5) いじめ・体罰 ゼロの取組
人権尊重の理念である「自分を大切ささとともに他の人の大切さを認めること」を常に意識し、子供の指導に当たる。教職員はじめ、児童、保護者に「いじめや暴力行為等の人権侵害は許されない行為である」という意識を高めていく。
- 人権教育プログラム、いじめ対策等を活用し、いじめ等に対する理解を深め、教職員の資質向上を図る。
- 道徳教育や校長講話等の充実を図り、いじめなどの未然防止・早期解決・早期解決に努める。
- 毎月のいじめ防止アンケートは、学校独自(4月、5月、7月、10月、12月、1月、3月)ふれあい月間(6月、11月、2月)実施し、いじめの早期発見、早期対応・解決に努める。
- いじめ案件が発生した場合、迅速にいじめ防止委員会を招集し、いじめの早期発見、早期対応・解決に努める。
(6) 不登校ゼロの取組
(1) 不登校ゼロに向けて教師は、「よく見る」「よく話を聞く」姿勢を保ち、子供に寄り添った指導をする。
(2) 不登校児には、常に保護者と連携を図り、最善の方法を模索していく。
(3) 不登校児とは、タブレット端末などを活用した「つながり」を続け、1週間以上間を開けないことに努める。
(7) 特別支援教育の理解と充実
(1) 校内委員会や生活指導全体会を通じて、配慮を要する児童について共通理解を図る。
(2) 特別支援教育や配慮を要する児童に対し、巡回指導員、特別支援教育専門員、特別支援教育コーディネーター、特別支援教育校内委員会を中心に、スクールカウンセラーを活用し、全教職員が共通理解に基づいたきめ細やかな指導を徹底する。
(8)「働き方改革」への取組
教育の質の向上を図るためには、すべての教職員の生活と仕事の両立・調和を目指し「ライフ・ワーク・バランス」の推進に向けて一層取り組んでいく必要がある。昨年度の実態を受け、今年度より以下のような改善を図る。
- 「すぐーる」運用による出欠席連絡、学校連絡配信、学校だより
- 学校評価のデジタル化による集計・分析の簡素化
- 学校だより、保健だより、献立表の配信
- 通知表の所見等の簡略化
学校を支えてくださっている保護者、地域の皆様、近隣校には、一定のご理解ご協力を求める必要がある。学校の都合だけで変えることはできない。しっかりと説明責任を果たしていかなければならない。「チーム柳小」として教職員一同が管理職に呼吸を合わせ推進していく。
特色ある教育活動
○朝学習、補充学習の充実による基礎基本の学力の確かな定着
○学年を縦割りにした異学年による交流活動
○特別支援学級と通常学級との交流および共同学習の推進
【みどりA学級(知的障害児学級)、みどりB学級(自閉症・情緒障害児学級)の設置】
○文教地区に位置する学校として、高校や大学との交流活動の推進
○芝生の校庭や敷地内の樹木・草花等の緑化による環境教育の推進
○保護者ボランティアによる活動による読書活動の充実
○地域との連携を深め、地域人材による体験学習の充実
○都立小平特別支援学校等との副籍交流の実施