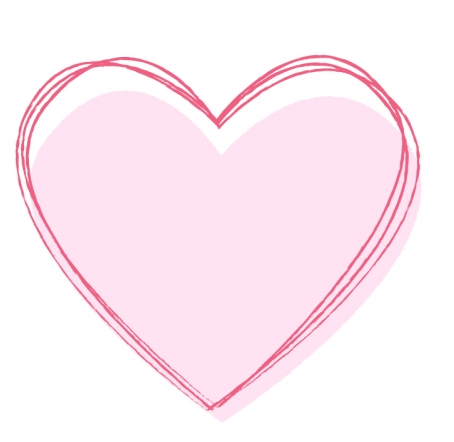学校いじめ防止基本方針
更新日:2025年4月18日
田無第二中学校の取組
1 基本的な考え方
「いじめ」とは、ある生徒に対して一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的影響を与える行為であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。なお、起こった場所は学校の内外を問わず、インターネットを通じて行われるものを含む。 いじめはどの学校でもどの学級でも起こりえるという認識の下に、日常的に未然防止に取り組む姿勢をもち、早期発見に努め、いじめを把握した場合は速やかかつ組織的に対応し、重大事態に陥る前に解決できるように努める。
(ア)個々の行為が「いじめ」にあたるか否かを判断する際は、表面的・形式的に行うこ となく、いじめられた生徒の訴えや悩みを暖か
く受け止め、いじめられた生徒の立場に立って行うものとする。
(イ)個々の教員がいじめに対する鋭敏な感覚と指導力、関わりをもち、それをバックア ップしていく学校全体の組織的な対応を行う。
(ウ)西東京市が掲げる「あったか先生」の基本理念を遵守し、教職員の人権感覚を高め る。また、担任一人がいじめ問題を抱え込むことがないように、組織で情報を共有し、対応する。
(エ)全ての生徒が安心して生活を送ることができるような学校体制を整えていく。
2 未然防止のための取組
(1)生徒への取り組み
(ア)「いじめは人間として絶対に許されない」という意識を生徒一人一人に徹底させ、 周りで傍観している行為もいじめる行為と同様であるということを認識させる。
(イ)特別の教科道徳や特別活動など、学校教育活動全体を通して、お互いを思いやり、 尊重し、自他の生命や人権を大切にしていく心の教育の充実を図るとともに、集団 の自治力を高め、「いじめを生まない土壌」づくりに取り組む。
(ウ)いじめの周りにいる生徒が「いじめを見て見ぬふりをしない」よう、日常的に特別 の教科道徳や人権教育を通して、生徒の自治力を高め、いじめの未然防止に努め る。
(エ)上記(ア)から(ウ)を行うため、年3回のいじめ防止授業を計画的に行う。
(2)教職員の取り組み
(ア)全ての教職員がいじめ問題に迅速、適切に対応でき、生徒の変化に気付くことがで きるように、年3回の校内研修での事例研究や、実践的な研修を行い、教職員の指 導力の向上を図る。
(イ)必要に応じて、ケース会議を実施し、いじめられる恐れのある生徒を徹底して守り 通していくための対策を検討する。
(ウ)校長のリーダーシップのもと教職員の役割分担や責任の明確化を図り、全職員が一 致協力した指導体制を確立する。
(3)保護者との取り組み
(ア)いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりをもつことから、PTAの各種会議や年度 当初の保護者会においていじめ防止基本方針を説明する。
(イ)学校Webページ・各種たよりを通して情報発信を行い、家庭での協力を伝えてい く。
(ウ)保護者や関係機関を対象としたいじめ(インターネット上のいじめも含む)防止のために、セーフティ教室や道徳授業地区公開講座等を活用した啓発活動等を推進する。
(4)関係機関との取り組み
(ア)管理職やいじめ対応の中心となる教員は、いじめ等に関する関係機関と情報交換できる指導体制をつくり、協力関係を構築する。
(イ)学校運営協議会にていじめ防止基本方針や本校の状況について説明するなどして、連携・協力体制を構築する。
3 早期発見のための取組
いじめは、大人の目に付きにくいところで行われる。ネット上のいじめの兆候は学校ではほとんど見えないことが多いが、早期発見は早期対応・早期解決につながるため、以下の事柄を確実に行う。
(ア)教師が児童生徒の悩みや変化に気付くために、あたたかく休み時間や昼休み、放課 後など、生徒とともに過ごす機会を積極的に設ける。
(イ)連絡帳などで生徒・保護者と日頃から連絡を取り合える手立てを工夫し、生徒を共 感的に理解し、相互の信頼関係を築いていくように努める。
(ウ)年3回以上のアンケート調査を実施し、生徒の声に耳を傾け実態把握に努める。
(エ)1学期、2学期はじめの相談週間にて、生徒一人ひとりから丁寧に話を聞き取り、 スクールカウンセラー、養護教諭による支援、特別支援教育(コーディネーター) を中心とした体制、情報の記録を行うなど、学校全体で生徒を守っていく。また、 保護者へ通信などでスクールカウンセラーの紹介を含め、活用方法などの情報を発 信していく。
(オ)生徒の動向を知るために、毎日の出席状態の確認や朝学活での生徒の様子、また、 給食指導での食欲低下などの日常生活の変化など、細かいところまで配慮を行き届 かせる。
(カ)担任任せにならぬよう、学年組織が情報を共有して生徒の様子を把握し、早期発見に努める。
4 早期対応のための取り組み
(1)初期対応の取組
いじめの初期対応は非常に大切なことであり、いじめられている生徒の苦痛を取り除くことを最優先に迅速な指導を行う。
(ア)いじめの疑いがあった場合は、対象生徒から複数教員での聞き取りを行う。
(イ)(ア)の内容について学校いじめ対策委員会で協議し、いじめの認知について検討する。※検討の結果、いじめと認知した場合は、市教委に第一報をいれる。
(ウ)学校いじめ対策委員会は、具体的な対応策を決定する。
(エ)対応する教員は(ウ)で決定された対応を速やかに行う。進捗状況について学校いじめ 対策委員会に報告する。
(2)被害生徒への支援
(ア)いじめにあった生徒に対しては、共感的なあたたかな態度で支援に当たる。
(イ)安心して学校生活を過ごしていけるように、授業中や休み時間には教員で見守りを行う。
(ウ)心理的なストレスを軽減するためにスクールカウンセラーとの面接など、具体的な手立てや、期間、担当を決定する。
(3)加害生徒への指導
(ア)いじめを行った生徒に対しては、担任や学年、スクールカウンセラーを中心とした 組織で、心理的に孤立感や疎外感を与えることなく、いじめの非人間性やいじめら れた人間の権利を侵害する行為であることを、毅然とした対応と、粘り強い対応で認識させる。
(イ)状況によってはいじめられた生徒を守るために、加害生徒への特別な指導や出席停 止措置を行う。
(ウ)暴行や恐喝など犯罪行為に当たる場合は、警察との連携を行っていく。
(4)重大事態の対応について
(ア)重大事態の定義
(a)いじめにより当該学校に在籍する生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認める時。 例えば、生徒が自殺を企図した場合、身体に重大な損害を負った場合、金品などに重大な被害を被った場合、精神性の疾患を発症した場合 等
(b)いじめにより当該学校に在籍する生徒が相当な期間欠席することを余儀なくされている疑いがあると認める時。
・不登校の定義を踏まえ、年間30日を目途とする。
(ア)重大事態への対応
(a)いじめられた生徒の安全を第一に考える。
(b)いじめられた生徒が落ち着いて教育を受けられる環境を確保する。
(c)学校内で発生の事実を留めることなく、速やかに教育委員会又は市長に報告し、連携した対処を開始する。
(d)学校に派遣された関係機関や臨床心理士等と連携した対処を行う。
(e)いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案については、田無警察署と連携した対処を行う。
(f)重大事態に係る事実関係を明確にするための調査の実施または市条例第11条に規定する「西東京市教育委員会いじめ問題対策委員会」が行う調査について協力する。
(g)重大事案の調査結果についての、市条例第12条に規定する「西東京市いじめ問題 調査委員会」が行う調査(再調査)について協力する。
5 組織的な対応の在り方
(1)組織的な指導体制
(ア)生活指導部を中心とした学校いじめ防止対策委員会を毎週実施し、いじめの有無の確認を常に行う。
(イ)いじめに対しての指導方針も統一し、教職員に対しての共通理解を図る。
(ウ)必要に応じて教育委員会や児童相談所、子ども家庭支援センターなど関係諸機関との連携をし、被害生徒のケアを図る。
(エ)加害生徒に対して継続的な観察と指導を組織的に行っていく。
(オ)保護者との連携を常に図り、いじめが完全に解決するまで組織として進行管理を行 う。
(カ)いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案については、田無警察署と連携した対処を行う。
(2)相談体制
(ア)生徒が教員・保護者に相談することは、相当の心理的負担を伴う事を理解し、生活指導部・特別支援教育の連携を密にして、被害生徒が安心して学校生活を過ごせる ように、細心の注意を払う。
(イ)授業中や休み時間の保護、心理的ストレスの軽減のためのスクールカウンセラーを 活用した心のケア、教育相談や子ども家庭支援センターなどの外部機関との連絡を行っていける体制づくりをする。
6 研修体制
いじめに対して初期の段階でその兆候を見逃さない目と、初期対応を含めた指導力を、校内研修を通して教員一人一人が高めていくことが大切である。そのために、年間を通して特別支援教育を実施していく。
(1) 研修は年3回計画的に行う。(重大事態や実践的な研修を行う)
(2) ネット上のいじめに対しても、セーフティ教室やリーフレット、DVD等を活用して 生徒に啓発していくとともに、教員と保護者による研修を行う。